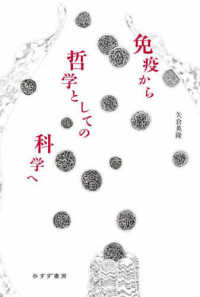内容説明
増加と停滞を繰り返す、4つの大きな波を示しつつ、1万年にわたり増え続けた日本の人口。そのダイナミズムを歴史人口学によって分析し、また人々の暮らしの変容と人生をいきいきと描き出す。近代以降の文明システムのあり方そのものが問われ、時代は大きな転換期にさしかかった。その大変動のなか少子高齢化社会を迎えるわれわれが進む道とは何か。(講談社学術文庫)
目次
原本まえがき
序 章 歴史人口学の眼
第一章 縄文サイクル
第二章 稲作農耕国家の成立と人口
第三章 経済社会化と第三の波
第四章 江戸時代人の結婚と出産
第五章 江戸時代人の死亡と寿命
第六章 人口調節機構
第七章 工業化と第四の波
終章 日本人口の二十一世紀
学術文庫版あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
43
縄文早期から現代まで、よくここまで日本の人口を推定できたな、という驚きの感想。わかりようがなさそうに見えながら、その推定の方法を聞くと、なるほど、かなりの説得力があるものだ。それにしても江戸の人々の平均寿命の短さ! 人生の意味と重みがまるで違う。私たちの人生観こそ、近年に新しくできたものであることを、しっかり捉えなければと思った。身につまされる本。2016/03/11
天の川
30
調べ物のついでに再読。豊富なデータで歴史を読み解いてくれる面白さ♪原始時代の遺跡からさぐる植生と人口のつながりも面白いけれど、宗門人別帳やお寺の過去帳…恐ろしく細かい内容の資料が豊富に残っている江戸時代は非常に興味深い。死亡率の高い季節とその原因、都市は人口を消費する場所で農村から人的資源が補給されていく。婚姻率の低さ、人口密度の高さによる疫病の広がりなどを考えれば、さもありなん。出産が死と隣りあわせだったことも全てデータで裏打ちされています。学者のデータ解析の執念たるやすごい!と変なところに感心しつつ…2014/09/10
樋口佳之
25
通説に反して、人口制限は真の困窮の結果ではないと見る立場が増えている。むしろ人口と資源の不均衡がもたらす破局を事前に避けて、一定の生活水準を維持しようとする行動であったというのである。その見方を受け入れるならば、堕胎も間引も幼い命の犠牲の上に、すでに生きている人々の生活を守ろうとする予防的制限/マクロな理屈はわかるけど、当時の妊娠出産の危険性を考えると、親の気持ちは今と変わらずやっぱりとても悲痛なものだったと思う。2018/03/06
太田青磁
21
人口動態こそ政治経済を表す指標であることを如実に感じさせてくれる読み応えのある一冊です。S字カーブとも言われるロジスティック曲線に歴史を重ね、文明のダイナミズムを新たな視点で感じることができます。都市への人口流入と人口調整の分析がとても興味深かったです。2012/12/15
月をみるもの
19
人類の歴史と文明を語る上で、最も重要なファクターのひとつが人口であることは言うまでもない。全編どこをとっても興味深いが、とくに印象的だった部分をいくつか引用:「宗門改帳の分析から江戸時代の堕胎·間引の行動を検討した人々のあいだからも、右の考えを積極的に支持する仮説が提出されている。すなわち堕胎·間引は、困窮の結果の行為というよりは、むしろ広義の産児制限に含まれる性質のものと見るべきだというのである」→続く2021/09/05
-
![私はシンデレラに殺された[ばら売り] 第2話 花とゆめコミックススペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2010324.jpg)
- 電子書籍
- 私はシンデレラに殺された[ばら売り] …
-

- 電子書籍
- 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者…
-
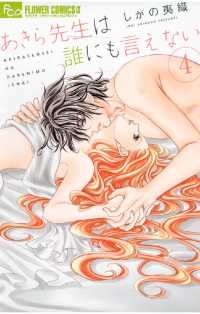
- 電子書籍
- あきら先生は誰にも言えない(4) フラ…
-
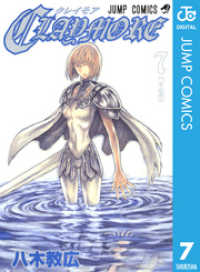
- 電子書籍
- CLAYMORE 7 ジャンプコミック…