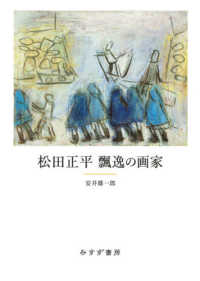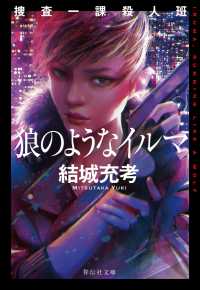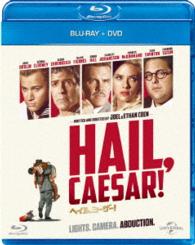内容説明
新進のうら若き女性哲学教師が教職をなげうち、未熟練の女工として工場に飛び込んだのは、市井の人びとの疎外状況を身をもって知るため、というだけではなかった。「人間のありのままの姿を知り、ありのままを愛し、そのなかで生きたい」という純粋かつ本質的な欲求による、やむにやまれぬ選択であった。だが、現実には激しい労働と限りない疲労に苛まれ、心身は限界に達する。過酷な日々を克明に綴った日記は問いかける、人間性を壊敗させる必然性の機構のなかで、はたして人間本来の生は可能なのか――。これは極限の状況下でひとりの哲学者が自己犠牲と献身について考え抜いた、魂の記録である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とよぽん
56
前半は、ヴェイユが工場で就労した記録が延々、日々の作業内容、成果、換算した時間給、扱いにくい機械、工場内の人間関係などなど苛酷な記述が続いた。なぜ、若い女性哲学教授が休職してまで、未熟練工として心身をすり減らして働くのか? ずっと疑問だった。あぁ、それは「労働を緻密に研究するため」にヴェイユが考え計画した最も有効な手段だったのだ。そして得られたのは「労働者は一切の権利というものも認められない。隷従は労働の中核」という現実。しかし、その経験によってトロツキーを論破したところで、すごい!と思った。偉大な人だ。2020/07/24
aika
53
心身をなげうってでも、過酷な現実に苦しむ人々の中に分け入っていくことを幸せだと言い切ったヴェイユの純粋な強さに心打たれます。持病に悩みながら、劣悪な環境で指から血を流し一女工として休みなく働く日々。彼女の目をとおして、生活の為に身体を壊してまで働かざるをえない人々の苦渋があまりに痛々しく、思考をやめてしまうことがどんなに恐ろしいことなのか思い知らされました。その一方で、作業に苦しむ彼女に向けられた、工員仲間の一瞬のほほえみや声かけが、どれだけ心の支えになったのか、温かい場面も綴られていたのが印象的でした。2019/04/07
ころこ
44
「シモーヌへの手紙」が巻末にあり、その他に解説もある。加えて序文もあり、その間にヴェイユの文章が入っている。彼女が様々な場所と時代の人たちから見守られているようだ。本文は書き付けのような断片であり、大半はアフォリズムではない。社会学者のやる参与観察ではあるが、読者が注目するのはそこではないだろう。観察している対象が自分であり、消耗した彼女の身体こそが言葉なのだ。ぼくは『アルジャーノンに花束を』を思い出した。上手く出来ない行為と、上手く出来る分析。読者は分析を読むが、気持ちを寄せるのは行為の方だ。2022/11/21
マリリン
28
現実を知るために自身の地位を棄て、一年間女工として過酷な労働に耐えた日々。なぜここまでして…という思いと、シモーヌにとって知るという事への情熱を感じた。人間を壊敗させるような組織の中に身を置きながらも、労働は芸術に等しい…とは。生きているだけでも価値がある…そう思わせる内容であるものの、前半の日記は読んでいるだけで辛くなった。2019/02/15
まると
27
こんなに純粋でストイックな哲学者がいたなんて衝撃です。鎌田慧さんが自動車工場に潜入したのは労働の非人間性を告発するためだったが、ヴェイユのそれは未熟練工の生活に身をやつし、そこで働く人たちと同じ苦痛を味わい、内面に訴えかけるためであった。日記を公にすることは考えてもみなかったはず。レーニンもトロツキーも工場を見ていないと疑問を呈し、自ら実践する。ノルマと能率給に支配される中、考えることをやめる誘惑に打ち勝とうと努め、苦しまなくなることこそが堕落だと結論づける。他者への愛情の深さ、並外れた行動力に痺れます。2021/06/07