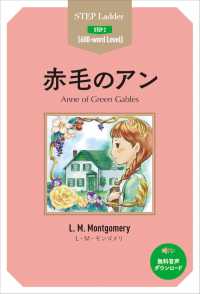内容説明
「憲法は常に未完の体系である」とは、憲法を正視した二人の共通のコンセプト。近視眼的な改憲論議を超えて、憲法学の大家と若き俊英が「想像力」で示す未来への針路とは。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
そり
18
民主主義における「民」とは、過去から現在、将来に生きるすべての国民のことを指すのだ、という言い方がなされることがあるという。広がりをもっているんだな、と嬉しくなった。単に、過半数さえ取れればいい、ではあまり知性が感じられない。今ある表面化した問題を見つつも、未来を見据えた視野も持ちたいと思う。でないと、重くなってかなわない。引用された、加藤周一さんがよく使っていたという「しかし、それだけではない」。僕も使っていきたい。2016/06/19
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
16
【15/10/23】憲法(の精神)を実現しようとすることは、ある楽曲を演奏することと似ている。単に楽譜通りに「正確」に演奏するだけでは人の心に届かない。伝えたいとする何事かがあってこそ、名演奏は生まれる。名演奏は、常に新しく生み出されていくものであって、その意味では名曲とはその時々において「未完成」なのである。また、名演奏とは奏者だけで生み出されるものでなく、よき聴衆あってこそ生まれるものである。ぼくも憲法のよき「聴衆」の一人でありたいと思う。Kindle版にて。☆3.8。2015/10/23
katoyann
15
2014年刊。安倍政権下で改憲論議が騒がれていた時期に編まれた、2人の憲法学者による対談集。憲法96条の先行改正案(改憲発議要件の緩和)が安倍元首相から提案された時期でもあり、政府が憲法改正を提案することの問題点について論じ合っている。奥平康弘は、旧来の学説が憲法の「司法権の優位」(違憲審査制)に注目するあまり、憲法制定権力が国民にあるという憲法の核となる理念を強調しなかったために、時の政権が改憲をリードしても構わないという発想が生まれたのだという。国民主権の強調が重要だったという訳だ。2025/01/29
勝浩1958
9
「「憲法は主権者たる国民が国家権力を管理するための法である」というのが、立憲主義の大原則です。ところが、自民党の憲法改正草案をくわしく読むと、その原則に逆行する記述が随所に目につきます。つまり、本来は主権者としての国民に管理される側の国家権力が、逆に憲法を「国民を管理するための法律」にしようとする姿勢が透けて見えるのです。」これは、恐ろしいことです。気を付けなければいけません。2014/07/19
まさにい
7
表現の自由を基礎から学び直そうと思い奥平さんの『表現の自由1~3』を買った。その流れで、古本屋で奥平さんの本を探していたらこの本が目に入り購入。一言でいうと、『いい本です』。思わずのめり込んで読んでしまった。憲法論というと難しい論理が展開されるが、この本は分かりやすく書いてあって、憲法を専門に学んでいなくても大意はつかめる。また、憲法を学んだ人にとっては、懐の深さが感じられるものである。このような本が多く出ていれば国民の憲法感覚も向上するのではないだろうかと思った。2023/01/07
-

- 電子書籍
- バスタード・ソードマン【分冊版】 29…
-

- 電子書籍
- オキビのタキビ 2 少年チャンピオン・…