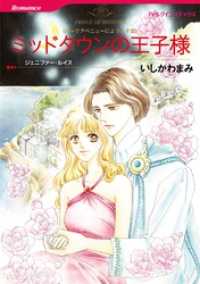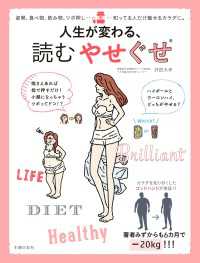- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
地理的な空間をどう認識するかは時代によって異なる。その違いを象徴するのが「地図」である。大きくみれば、江戸時代は日本の「かたち」が地図上で整えられた時代であった。前期は、中世的な感覚にあふれ、観念的に日本の「かたち」が表現された。後期になると、政治や社会の変化にあわせて日本がとらえられるようになる。本書では、江戸時代の日本地図の変遷をたどり、現代の日本の「かたち」がいかにつくられたかを探る。近世史の知られざる側面を照射し、歴史地理学の世界へ読者を招待する一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
13
江戸時代の地図という反射的に「伊能図」となってしまいますが、社会的なインパクトという点から言えば長久保赤水の『日本輿地路程全図』のほうがはるかに大きかったんすな。石川流宣にいたっては、この本で初めて存在を知りました。。東洋文庫の「大♡地図展―古地図と浮世絵」も、まだしばらくやってるんで、こちらもぜひ http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/exhibition.php2018/12/01
ふろんた2.0
12
江戸時代の地図史だったのね。ちょっと勘違いしてた。神保町に古地図を専門に扱う店があったなあ。2015/10/28
浅香山三郎
10
江戸時代と地図といふと、伊能忠敬あたりを思ひ浮かべるのが平均的なところだが、本書は美しさから正しさへといふ二つの観点の間の重心移動から、中世の行基図からの脱出、流宣日本図、赤水日本図といふ流れを読み説く。忠敬は、5章の後半に出てくるだけである。 権力の作らせる地図と、刷り物の地図の関係、何を情報として書くか、或ひは江戸の出版文化といふ広い視野から地図を読む愉しさが味はへる。石川流宣といふ人物については全く知らず、菱川師宣の弟子からかういふ人が出るとは、事実だけから言ふと、いささか意外だつた。2017/05/22
スズツキ
9
日本の地図史は江戸時代を境に劇的に変化したと指摘する著者の日本古来の思想や文化的背景を考慮に入れた歴史書。奈良時代の行基を祖とする「絵」の地図が江戸時代に「図」に反転する様、芸術が重視された古代から正しさが重視されるようになった経緯が面白い。2015/12/06
なおこっか
5
むちゃくちゃ楽しかった!いつ誰が何の意図で地図を作ったかという明確な縦糸に時代背景もからめ、江戸時代以前からの流れを追う。幕府、出版、個人作成地図各々に言及あり、ふわっとした江戸時代括りの本とは一線を画す。/江戸以前からの主流は行基式日本図。行基が歩いて日本は独鈷の形と見出した、との伝承から命名。日本を海岸線から捉えるのではなく、国のまとまりとして描くのでぽこぽこした見た目。/16世紀頃航路が発達し商港情報が重要になり、入江の表記も詳しくなる。特に九州は海外とも往来あり詳細。逆に瀬戸内の輪郭はゆるゆる。2025/03/24