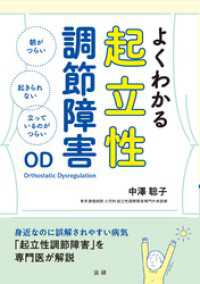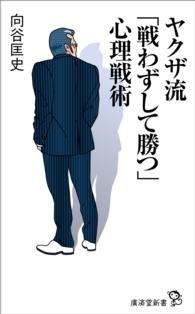- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
日本の相対的貧困は、およそ2000万人――。75歳以上の後期高齢者よりも多いこの国の貧困層は、この先3000万人まで増えるとも言われています。そしてこの病巣は静かに、けれども急速に、日本に暮らすあらゆる人々の生活を蝕み始めています。
ひとり親、女性、子供…。これまで貧困は、社会的弱者の課題として語られることが多かったはずです。けれど貧困は今や「一部の弱者の問題」として片付けられる存在ではなくなっています。
困窮者の増加が消費を減退させ、人材不足を進め、ひいては国力を衰退させる――。
経済記者が正面から取り組んで見えてきたのは、貧困問題が日本経済や日本社会に及ぼす影響の大きさでした。「かわいそう論」はもう通用しません。求められるのは、貧困を「慈善」でなく「投資」ととらえ直す視点の転換です。企業やビジネスパーソンにできることは何か。貧困を巡る日本の現状と課題、そして解決の糸口を「経済的観点」から分析した初のルポルタージュ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
nyaoko
74
格差社会は今に始まった事じゃないと思うのね。いつの時代だってあったのよ。お金のある人は昔からあるし、無い人は無い。でも、お金が無い=貧乏は生きていけれるけど、貧困は違う。命に関わる。この時代になっても貧困の連鎖が止まらないって事は本当に危機的状況で、引いては国力低下にも繋がるのね。その為には子供の頃からの支援じゃなくて、その、子供を産むであろう親世代から支援をしなくちゃ間に合わない。なのに、そういった経済的支援を行う企業がこの国には殆ど無いって、なんかもう、情けないとしか言いようがないよ。2018/03/16
ヒデミン@もも
41
延長して借りた。わかりやすいから購入。タイトルにある『必要なのは「慈善」より「投資」』が戦略的だけれど、内容は至極真面目。日経だもの。特に著者の真摯な考え方に惹かれた。貧困の連鎖をたつにはやはり幼児期の教育と環境が大切。2016/07/17
壱萬参仟縁
35
数字の大きさと実感との乖離に驚きがある。貧困拡大は社会全体の問題(6頁)。ネットカフェ月の家賃が6万円。これには光熱費、通信費、ドリンク代込みとのこと(21頁)。生活保護4兆円(32頁~)。誰も彼も大学に行くのが人生ではない(72頁)。そんなことはないだろう。生涯学習とか言ってるでしょ。カネがないだけで諦めることはない。私は学部時代、1.5年分の学費は還付されたことがあります。そのカネで大学院に行けたかもしれないが。2015/11/29
onasu
32
日本には貧困層が2000万人以上いるとは、驚くべき数字だ。それでもまだ大きな社会問題化していないのは、私感では、物価が安いことと、今はまだ家族の扶助があるため。だが、これもそう長くは続かない。 大学全入時代と言われる中の学費の高騰。2.6人に一人が何らかの奨学金を受給しており、学力の足らない者も多ければ、就職もままならず、滞納も増えている。 貧困問題をもう、自己責任だの、他人事だの言っていては、そうでない人たちに影響が及ぶ時が迫っている。その対策は、国の将来への投資として考えるべき時にきている。2015/12/15
ヒデミン@もも
29
社会福祉論の課題のため再読。2017/07/30