- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
AMS炭素14年代測定に基づき、水田稲作の開始は従来よりも500年早かったとした国立歴史民俗博物館の研究発表は当時、社会的にも大きなセンセーションを巻き起こしました。発表時には当時の常識からあまりにもかけ離れていたために疑問を呈する研究者も数多くいましたが、その後、測定点数も4500点ほどまでにと飛躍的に増加を遂げ、現在では歴博説の正しさがほぼ確定されています。では、水田稲作の開始が500年早まると、日本列島の歴史はどのように書き換えられるのでしょうか。一言で言えば、「弥生式土器・水田稲作・鉄器の使用」という、長らく弥生文化の指標とされていた3点セットが崩れ、「弥生文化」という定義そのものがやり直しになったと言うことです。この3つは同時に導入されたものではなく、別々の時期に導入されたものでした。例えば鉄器は水田稲作が始まってから600年ほど経ってからようやく出現します。つまりそれ以前の耕作は、石器で行われていたのです。また水田稲作そのものの日本列島への浸透も非常に緩やかなものでした。水田稲作は伝来以来、長い間九州北部を出ることがなく、それ以外の地域は依然として縄文色の強い生活様式を保持していました。また東北北部のように、いったん稲作を取り入れた後でそれを放棄した地域もありました。関東南部で水田稲作が始まるのは、ようやく前3~2世紀になってからでした。とすると、これまで歴史の教科書で教えていたように、何世紀から何世紀までが縄文時代で、その後に弥生時代が来ると単純に言うことはできなくなります。水田農耕社会であるという弥生「時代」の定義は、ある時期までは日本列島のごくごく一部の地域にしか当てはめられなくなるからです。本書は、このような問題意識の元で「弥生文化」が日本列島に浸透していく歴史を「通史」として描く初めての本です。(講談社現代新書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
白義
fseigojp
月をみるもの
おせきはん
-

- 電子書籍
- 狼と香辛料亭 グルメ探訪記【分冊版】 …
-
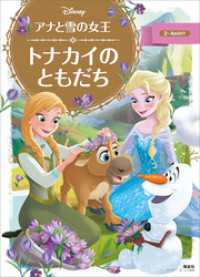
- 電子書籍
- アナと雪の女王 トナカイの ともだち …
-
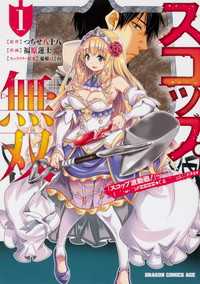
- 電子書籍
- スコップ無双 「スコップ波動砲!」 (…
-
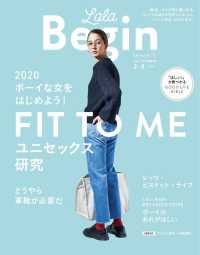
- 電子書籍
- LaLaBegin - Begin2月…





