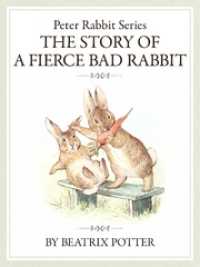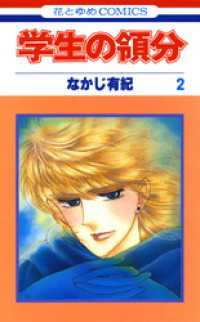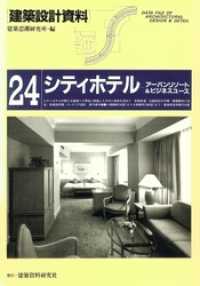- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
いつも時間に追われていて、思うとおりに物事が片付けられない。それなりの収入はあるのに、目の前の出費のために、借金を重ねてしまう。ダイエットをしようとたびたび取り組むけれど、長続きしない。人の気を引こうと熱をもって話しかけるが、いつも相手はつまらなそうなだけ。薬を処方通りキチンと飲まないから、いつまでも治らない。こうした、同じ状態から抜け出せない人は多いですが、じつはこれらはすべて、必ずしもその人の資質によらない、ある共通の要因がもとで起こっていたのです。さまざまなめざましい実験・研究成果を応用し、期待の行動経済学者コンビが初めて世に贈る一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
239
この本を手にとった時は時間の管理方法について書かれていると思ったが、副題を見ると行動経済学だったので読むまで気付かなかった。さて本書では空腹やローンの返済などの欠乏という心理状況がいかに人の判断を誤らせるのかという事例をたくさん書いていた。正しい判断をするというのは中々いろんな要因が出てくると難しくなるのだとわかった。2015/03/15
yomineko@鬼畜ヴィタリにゃん🎄🎅🎄
67
いつも時間がないと思ったり、言っている私は「スラック(予備の時間。yomineko訳)」を作らず、いつもギリギリ状態で仕事を進めたり、語学の勉強をしているのでどこかでしわ寄せが来る。そして、「トンネリング状態(やるべき事をトンネルの中にしまっていて、気付かないふりをしてしまう。yomineko解釈)」に嵌ってしまう。この本は講堂経済学という難しいテーマを掘り下げた名作。日本語訳がやや硬く感じるが、理路整然としていて分かりやすい。ギリギリで予定を立てると必ず失敗すると分かっていてもやってしまうのが人間。2021/06/19
Willie the Wildcat
58
行動経済学からの「欠乏」とその影響。時間とお金という物理面より、精神面の余裕の有無と解釈。トンネリングvs.スラックは聞き慣れているが、「マインド・ワンダリング」は確かに要注意。本能からのリスク回避への警鐘に近いのかもしれない。但し、対策が割りと普通なのが意外でもあり、納得感もある。一方、違和感が拭えないのが「貧困」への論旨展開。論理ではなく感情面。事例も豊富だが、十把一絡げの表現がどうにもなぁ・・・。2015/11/23
Koichiro Minematsu
42
トンネリング、欠乏が欠乏を生む2023/07/01
ふろんた2.0
28
実用書かと思っていたら、行動経済学の本でした。常に欠乏状態であると、次第にパフォーマンスまで低下して、ジリ貧に陥ると。常にゆとりを待たせておくことが必要。2016/03/01