- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
科学は、何を生命として捉え、分析してきたか? 現代生物学が拠って立つ論理と成立構造とは? 「遺伝子」概念が孕む揺らぎとは? ダーウィン以前から、分子生物学や遺伝科学が急速発展するポスト・ゲノムの現代まで「生物学」の成立過程を辿り、「科学の見方」を哲学の視点から問い直す、生命のエピステモロジー。(講談社選書メチエ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やまやま
10
「ひと」が認識する生命とは、まずひとの生命とはこういうものというあり方の認識が先にあって、他の生命のあり方をそれに基づいて解釈する、といえば、何となくチョムスキーを思い起こす人もいらっしゃるかもしれません。「あらかじめの知」ということに証明は難しいと思いますが、我々は我々に「似た」ものに生命を見出す(認識する)ので、擬人主義を避けずに、まずはひとはひとの生命をどう認識するかから入って、それを他の生命にどこまで妥当に当てはめることができるか考える、という著者の考えはそれなりに魅力ある説明と思いました。2022/11/12
つみれ
2
タイトルくらいしか見ずに手に取ってしまったので、もっと古代からの話になるのかなと勝手に思ってたら凄く最近の話から始まるのでびっくりしたけども、逆にとても最近まで、今から言うとオカルティックな考えだったんだなって。▼合目的性をこっそり持ち込んでいた辺りからめちゃくちゃ面白い。2021/07/05
彦坂暁/Hikosaka Akira
2
とても面白く読んだ。ぼくらはよく素朴に「生命は物理・化学の言葉で説明されるべきだ」みたいに考えたり、「遺伝子の機能を調べる」とか「生命は情報機械だ」みたいなことを言ったりするけれど、本書はそういう現代生物学/生命科学のものの見方や、生物学で用いられている様々な概念について、その起源や前提を問いなおして、批判的に検討している。とくに第4章「機械としての生命」のあたりの議論はとてもスリリングでした(ぜんぶ納得したわけではないけれど)。「自分はいったい何をやっているのか」を問い直してみるのは、現役の生命科学者や2012/01/17
あいうえお
1
とある必要性に迫られて、流し読みながら。「遺伝子の論理」からの分析が必要という点が、興味深い。2017/11/29
-

- DVD
- 人妻拷問
-
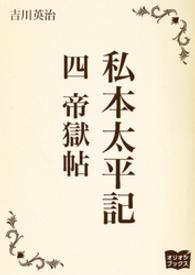
- 電子書籍
- 私本太平記 四 帝獄帖




