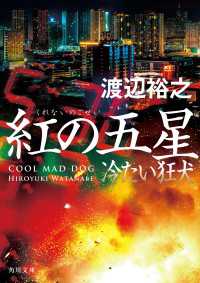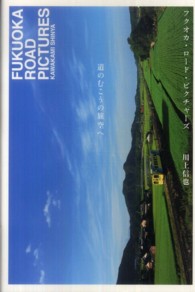- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
選書日本中世史 第3弾! 公家政権と武家政権と寺社勢力……室町幕府の傑出した統治構造とは!? 室町幕府にできて、鎌倉幕府にはできなかったこと。それは、「太平の世」前夜の、動乱の続く地方に対して中央政権として安定的に君臨することである。そのために室町幕府が考え出した統治構造とは? 自明のものとされてきた将軍の主従性的支配権に一石を投じ、天皇・公家の持つ力の本質を検証することで、明らかになった将軍権力とは、いったいどんなものだったのか? 「わかりにくい中世をどうわかりやすくするか」の大問題に真っ向から挑む、刺激に満ちた1冊。(講談社選書メチエ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
23
「鎌倉幕府と室町幕府はどこが違ったのか」という問いから始まり、終章でばっちりその答が出ているから、最初と最後だけ読むと実にすっきりしている。中途で色々な議論(禅宗の展開や康暦の政変など)が挟まり却って分かりにくくなった感があるが、各論も充分に面白いので頑張って読みましょう。朝廷から距離を保った鎌倉幕府に対し、アウェイの京都を本拠としつつ天皇や公家衆と渡り合った室町幕府。考えてみれば、歴代幕府の中で朝廷に打倒されなかったのは室町だけなんだよなあ。2025/06/21
bapaksejahtera
18
武家政治の基を開いた室町幕府について、先行する鎌倉幕府との対比に基づきその政治権力の本質を分析する。比較的柔らかい話題で中世社会を描く著者の本を読んで来た読者にはやや難解である。なぜ我が国は天皇制を放棄しなかったかという疑問が本書の背景にある。近代合理性とは乖離した宗教社会で、支配の円滑を図るには、仮令高師直等の新支配者が時に矛盾を吐出そうと、文書書式を含む有職故実を掌握し政治支配の難題に即応する回答を捻出す伝統は、主従性的支配と統治権的支配の矛盾を止揚した。Mウェーバー流の官僚的支配の代替物だったのか。2023/02/24
feodor
6
室町幕府論の一つ。鎌倉幕府と室町幕府の比較論から、室町幕府のシステムというか統治機構を見ていく論考。公・武・寺という三種の権力機構が組み合わさったもの、という印象がある。官宣旨・太政官符などの文書行政にみる公(朝廷・貴族社会)の全国的支配を前提とした組織、地域的支配を軸とした武家組織の融合が、義満幼少時の細川頼之管領時代を中心に描かれている。室町幕府が全国支配をあきらめて地方政府同士の「外交」を通じた間接支配に至った、というのはなるほど……と思う。2011/04/05
かわかみ
5
2010年に出版された図書であり、その時点での有力な学説が紹介されたり、自分にとって初めて読むようなエピソードが多くて面白く読めた。ただし、標題の将軍権力については結局深掘りできていない。管見では、本書の10年後、2020年に出版された桃崎有一郎「室町の覇者 足利義満」が室町幕府の権力が生成した歴史的プロセスをよく捉えているし、2021年の伊藤俊一「荘園」が権力の経済的土台について詳述している。本書は政治権力を政治の面だけで完成した姿から、公武の対立構造として分析しているので本質に辿り着いていない。2023/08/15
mushoku2006
5
本著は、「わかりにくい中世をどうわかりやすくするか」の大問題に、真っ向から挑まれた、刺激に満ちたものになる筈だったらしいんですけど、その試みは、少なくとも私にはさっぱり。全然わかり易くないし、刺激も受けませんでした。 細川頼之のところで、「守護大名のための幕府」を目指したという説と、五山禅林が室町幕府にとっての中央銀行の地位を獲得したという説は、とても興味深いのですが、いかんせんそこのところの詳しい説明がなく、具体的にどういうものだったか?さっぱりわからなかったし、説得力が乏しいとも思いました。 2014/08/20