内容説明
この不可思議な芸術が持つ“魔力”の根源への探究。空気の波動である音が、時に甘美に心を溶かし、時に激しく魂を揺さぶる魔法となる。この不可思議な音楽というものの正体を、クラシックをはじめ、ロック、民族音楽などの多彩な音と音楽学にとどまらない多様な視点から探究する。すべての音楽好きに贈る、あざやかでかろやかな論考。(講談社選書メチエ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おおにし
9
うーん、引用されたクラシックの楽曲を知らなかったり、楽譜が読めない私にはちょっと難しい本であった。唯一「音楽がハーモニーである」という章で、スティービーワンダーの「心の愛」のサビの部分が何故心に沁みるのかを解説した部分だけはコード進行の話だったので理解することができ説明に納得できた。2012/12/27
ポカホンタス
3
何げなく目に留まって買った本。読み出したら面白い。音楽は魔法である、システムである、表現である、リズムである、旋律である、ハーモニーである、コミュニケーションである。これら7つのテーゼにしたがって、音楽の本質を深くかつ平易に語りかける。いい本に出会った。2012/06/03
HK
1
音楽は魔法で、かつシステムでも、表現でも、リズムでも、旋律でも、ハーモニーでも、コミュニケーションでもあるという結論である。考古学から現象学(哲学)まで持ち出して説明している。気合が入った真面目な記述ではあるが、すこしすそ野を広げすぎた感じがある。個人的には、リズムの部分が最も興味深かった。2019/10/18
ありさと
1
思いがけず倫理哲学に行き着いた。音楽を多面的に解釈し、再び集約することで全体を描き出そうとしている。平易で伝わりやすい。自分の思考の整理の助けにもなった。2014/12/13
またの名
1
平易だけどしっかりと音楽の本質をとらえようとする、なかなかの良書。考古学的・人類学的・現象学的考察を組み合わせながら音楽の起源や表現装置としての機能に迫ってみたり、(西洋)音楽の基本概念を解説したり。デカルトの情念論とバロック音楽の関係性は「へぇー」という感じ。知らない曲や楽譜はネット時代の利器を利用してその都度確認。ベルクソンの哲学に大きく感銘を受けているという著者になんとなく親近感。(そういえば木村敏も音楽からベルクソンに向かったとか)2013/06/17
-

- 電子書籍
- ゲーム悪役貴族に転生した俺は、チート筋…
-
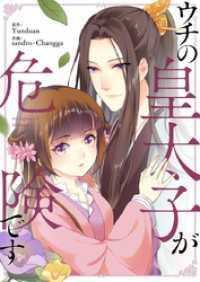
- 電子書籍
- ウチの皇太子が危険です【タテヨミ】第1…
-

- 電子書籍
- 志賀直哉・天皇・中野重治 講談社文芸文庫
-

- 電子書籍
- ネットワークマガジン 2003年12月…





