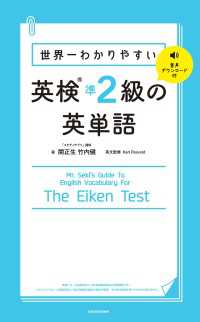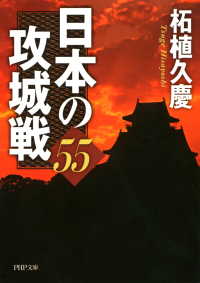内容説明
木山捷平は、昭和三十年代後半から四十年代前半の彼の晩年ともいえる日々を、日本中を旅する取材執筆に費やした。北海道から九州まで、日本の津々浦々を巡り「新しい紀行文」を書き続け、それは詩や小説にも昇華した。それぞれの土地に、死の陰を刻みながら・・・。初めての北海道旅行での詩「旅吟」から、病床で書かれた最後の詩「オホーツク海の烏」を収録、二九篇厳選。
目次
旅吟──北海道
銀鱗御殿の哀愁──北海道
登別──北海道
オホーツク海の味──北海道
霧笛の旅路──東京─北海道
ノサップ岬──北海道
椎の若葉──青森
太宰の故郷──青森
秋田美人冬の孤独──秋田
原始的なトルコ風呂のメッカ──岩手
中央競馬・福島夏の陣──福島
阿武隈の国民宿舎──福島
日本海の孤島・粟島──新潟
夜のお江戸コース──東京
上野駅──東京
伊豆の春──静岡
長寿と野猿の天国──静岡
信玄の隠し湯──山梨
伊良湖岬──愛知
“おのころ島”タンケン記──滋賀
城崎の思い出──兵庫
天理と高野山の春──奈良
おみくじ巡り──奈良
ふるさとの味──岡山
奥津と湯郷──岡山
長門湯本温泉──山口
西海の落日──長崎
旧婚旅行──宮崎・鹿児島
オホーツク海の烏──北海道
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ただいま蔵書整理中の18歳女子大生そっくりおじさん・寺
82
また読んだ木山捷平。『大陸の細道』という長編小説で賞をもらってからようやくブレイクした木山捷平、この時57歳。63歳で亡くなるまでの数年間に執筆依頼が殺到。その中には紀行文もあり、本書の旅は全てその晩年数年間のものである(岡崎武志の解説に詳しい)。私は旅行記を読むのが苦手なのだが、木山捷平ならば読みたい。本書に関わらず木山捷平の本を読むとしばしば感じるのがその差別の無さ。どんな人にも気さくに話しかける。旅館での若者の夜中の騒ぎ声にも「いつ聞いても若い人の声はいいものだ」と寛容の極み。この優しさが良いのだ。2019/09/14
アキ・ラメーテ@家捨亭半為飯
40
晩年、売れっ子になってからの紀行エッセイ。高度成長期の日本全国津々浦々。今よりも旅は時間もかかっただろうけれど、列車で隣り合った人や旅先で行き会った人と親しく話している様子に昔の旅はこんな風だったったんだろうな……。匂いがある文章に旅情をかきたてられ、書いてあるこの時代のこの場所に行ってみたいとタイムマシンでもないと実現不可能なことを考えてしまった。今はもうこの紀行文が書かれた土地もすっかりその頃とは変わってしまっているだろう。2016/09/06
RYOyan
13
読み進めるうちに、散りばめられたユーモア(ちょっとブラック!?)の魅力に気がつきました。今よりはきっと活気のあった昭和40年前後の田舎の雰囲気が味わえます。2016/03/03
hitsuji023
10
まったくこの著者の予備知識なしに読んだ。本のあらすじにある「死の陰を刻みながら・・・」という感じは全く無かったのでどういうことなのだろうと読み終わりに思った。地元の人とのインタビュー形式の会話文から真面目な印象を受けた。派手な内容ではないけれど著者の人柄がにじみ出た紀行文。2017/01/07
軍縮地球市民shinshin
9
解説によると、木山捷平が脚光を浴びたのは晩年になってからだったらしい。経済的と健康の理由で旅行は晩年になるまで木山はできなかったようだが、旅行雑誌の依頼で北海道から宮崎・鹿児島あたりまで旅をした際の紀行文を集めたもの。木山は旅先で一緒になった人びとに気さくに話しかけていろいろな話を聞いている。それがまた面白い。昭和30年代~40年代初頭だが、当時の日本人は知らない人から話しかけてもちゃんと答えていたんだなぁと思った。今だったらこういう風にはいかないんじゃないかと思った。佳品である。2018/03/31