- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
桂米朝の落語は、速記、本人執筆による論文、エッセイが数多く刊行されている。それらは落語という芸能全体について後世に遺される貴重な資料となっている。筆者は中学生のころラジオ番組のリスナーとして米朝と出会い、その後、門人の桂枝雀に台本を提供したことから、米朝からも親しく教えを受ける機会を得た。「桂米朝落語研究会」の反省会、米朝が一門の落語を聞いた後、丁寧にダメ出しをしていた場などにも同席、教えの一部を垣間見、ノート10冊に書き留めた。上方落語中興の祖・桂米朝の芸談、ネタや本人にまつわるエピソード、古い芸人たちの思い出話などを、演題解説とともにつづる。また米朝の、活字、音源、映像についての莫大な資料情報も掲載。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
119
米朝さんや四代目米團治師匠の全盛の頃の落語を聴きたかった。落語について語られていることも奥が深い。「京都の東の方は、米朝さんがお弟子さんの落語会と反省会をされていたところだから、僕らが話しても笑ってもらえないというか、お客さんの目が厳しい…、けどお客さんかて米朝さんとは違うんやからもっと笑うてくれても…。御池辺りの真ん中で落語すると笑うてくれますねぇ(笑)」と京都の独演会でタマさんがマクラで話されていたのを思い出した。だから、タマさんは、米朝さんの十八番の「地獄八景亡者戯」を選んだのだと今頃納得。2017/01/27
ぐうぐう
24
『枝雀らくごの舞台裏』に続き、今度は師匠である米朝を、ベスト40席の演題から語る。あとがき執筆中に米朝の訃報に接し、結果的、追悼刊行となった。読み終えて思うのは、米朝の落語に対する繊細さだ。声のトーンの高さ、ほんの短い間があるかないか、その些細な違いで、噺にリアリティが出るか損なわれるかが決まる。その繊細さがあったからこそ、米朝は名人となり、多くの噺を復活させることができたのだということが、本書を読むとよくわかる。(つづく)2015/06/14
六点
21
ぬこ田はオジサンなので、米朝といえば『味の招待席』であるが、この本も座付作者として米朝と深い交流があった著者による米朝の演目解説に名を借りた、芸談とエピソードによって構成されている。『枝雀』では「落語という話芸のさらなる発展」に身を砕いた枝雀師匠の姿が描かれているが、この本では戦後すぐの困難な状況にある上方落語の存在を社会に認知させ、古典の発掘(と言う名の創造)後進の育成などありとあらゆる面で現在の上方落語を作り上げた米朝師匠の、芸道の追求からの厳しさやいらちの理詰めぷりまで「芸人」米朝を見ることができる2019/02/11
遊々亭おさる
18
2015年3月、上方落語中興の祖にして人間国宝の桂米朝師匠が亡くなった。これで四天王の中でご存命なのは春團治師匠ただひとりとなり、まさに昭和は遠くになりにけり。落語作家で米朝師の弟子、枝雀さんと親交が深かった著者が米朝師から伝え聞いた古き良き時代の上方芸能史。この師匠ありてこの弟子あり。芸事に対するあくなき探求心とお弟子さんや近しい者に見せたお茶目な一面を垣間見れて人間国宝の生の魅力に触れられる一冊。巨星落ちても音源や著作は残る。上方落語の本質に触れたいならば、まずは桂米朝をあたるべし。2015/06/30
かもい
17
書き終えてから米朝師の訃報にあたり、追悼刊行となった一冊。あとがきにもある通り枝雀編とは違い一歩引いた体裁になっているが、先代米團治師や上方落語復興期のエピソードも多く語られ噺家・米朝の功績と歩みを感じられる。それ以外でもお茶目なエピソードや薀蓄、聞いたことの無い小咄・艶笑噺など話題が豊富で存分に堪能しました。しかし学生の頃から記録を取り続けている小佐田さんも上方落語に欠かせないお方だなあ。2015/12/06
-

- 電子書籍
- 璃寛皇国ひきこもり瑞兆妃伝 日々後宮を…
-
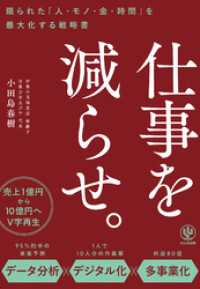
- 電子書籍
- 仕事を減らせ。 限られた「人・モノ・金…
-

- 電子書籍
- 波動の秘密 宇宙のしくみで人生を動かす…
-
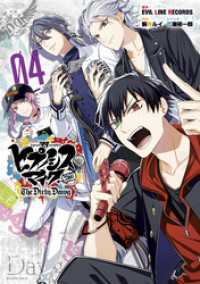
- 電子書籍
- ヒプノシスマイク -Before Th…
-

- 電子書籍
- マーガレット 2019年20号




