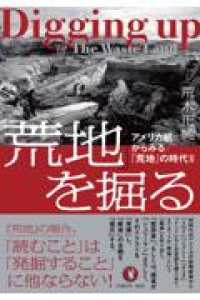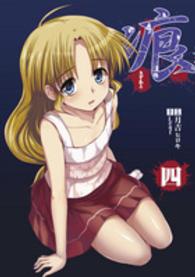- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(教育/子育て)
内容説明
「うちの子はまるで聞き分けがない」「お利口すぎて逆に不安」「泣き言を聞いていると私まで苦しくなってくる」etc・・・。子どもの激しいダダこねに悩み・不安を抱えるご両親へ、ダダこねの本質を解説し、カンシャクのなだめ方、ダダこねとのつきあい方を指南。親子の絆と子どもの自立を育てる一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みそしるちゃん
3
★赤ちゃんのころには目立たなかった激しいだだこねや癇癪を見ると「子どもが急にワガママになった」という印象を受けるが、そうではない。子どもの幸せな成長にとって欠かせない自我が芽生えてきたことの表れ。 ★子どもは4歳を過ぎたらもう社会人。話すことで家族の一員としての責任を果たすこともできる。1歳~4歳はいわば「思春期」ともいえる。人と対等に互角につきあうための自己主張と抑制を学ぶための「反抗」「だだこね」 ★共感し、なだめ抱きしめる。口と体を使って対話すると自尊心が満足し、納得ずくの自制心を養える。2012/01/23
alpha_zero
2
ダダをこねられるとつい原因を探したくなるのですが(親がそうだったので)、そうじゃなくてただ気持ちに寄り添うだけの方がいい時もあるのだということが知れただけでも読んでよかった。折に触れ読み返したい2015/04/23
もーちゃ
2
子育て中のご両親には読んでいて損はないと思う。ダダコネしてる子供に対しての向き合い方が楽になると思います。2013/09/05
のん@絵本童話専門
1
結構今の私にグサリと刺さる内容でした。長男小三ですが、ダダこねさせてあげられた気が全くしません。長らくダダこねが抑制されてきたのではないか。一様にこうしたら良いという方法はないけれども、目標やヒントは本中に示されています。1歳半〜3歳の最もダダこねの激しい時期の子へ向けた育児書でもありますが、その時期を過ぎて手こずっている子に向けての指南書でもあります。ダダこねができる親子関係を。ダダこねを受け止めること。大きい子の癇癪に悩む方にもヒントになるかもしれません。2021/06/07
Baku73
1
今まで読んだ育児書の中で一番良かったと思えた本 甘えと甘やかしの違いを理解してこそ始めてできるだだこねの受け入れ方。だだこね・癇癪は悪いことではない!とにかく子どもの泣きたい気持ちに寄り添う!!を徹底。1週間も経つと激変。子どもが驚く程落ち着き癇癪を起こさなくなっていた。育児者が子どもの気持ちを理解し、適切な対応するだけで子どもはすぐに変わることまた育児の面白さを知った本。 支援センターや保育士の友人達に幾度となく相談してもよい策が見つからず、頭には500円玉以上の円形脱毛ができた私の救世主です。2018/09/20