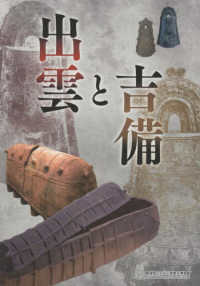- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
大学には入ったものの、何をしたらいいのか、何がしたいのかがわからない君たちへ――本書は、「大学は自分をつくる最初の実験場所」と語る札幌大学教授の著者が、いい教師の見つけ方、留学の効用と危うさ、学びたくないものを学ぶ効用など、大学という場を最大限に活かす方法をアドバイスする。「自分の大学にいい教師を見つけるのは難しい。“読者”になろう。“弟子”になろう」「若いときに、異物や異界と触れることで、価値観の違いや交際すべき人間がいることのありがたさを実感できる。最上の契機が留学だ」「何を学びたいかは、ある程度学んでみなければわからない」など、モラトリアムの大学時代にこそ大切な考え方を具体的に提言。悩もうと悩むまいと、学ぼうと学ぶまいと、同じように卒業資格が与えられる日本の大学。若い時代の大切な4年間を無駄にしないための鷲田流「学問と人生」の指南書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さい
2
最近の大学生は友人とのコミュニケーションを非常に大事にする。人との付き合い方に悩んで模索して生きてる。一方、学問だとか、社会の物事への関心が薄い。昔の大学生は学問だとか、社会の物事への関心は非常に深い一方、コミュニケーションについてはそれほど悩んでいない(割り切っている)。興味深い。2014/02/02
topaz
2
共感できない内容が多かったかもしれない……。学ばなくていいことはないということは参考になった。また、様々な分野を学ぶようにし、そのために自分の主専攻以外に副専攻を持つとよいとのこと。2011/10/05
海歌@旧アカウント
1
大学の課題図書。2016/05/10
ペーター
1
タイトルに釣られて読んでしまったが、内容の大半は筆者の独自理論自慢(言い方が悪いけど)。この本は5章構成なのだが、1章めがその内容だったので「ん?」と思いながらも読み進める内にタイトルに近い内容になっていった。内容は「あぁ、まぁ、一理あるな」くらいの感想だが、「二兎を追う者は三兎を得る」の小見出し部分だけは読む価値があると思う。そもそもこの本は98年刊行の本を改題したモノだし、具体的な情報を手に入れたい人は新しい本を読んだらいいだろう。2014/03/18
ふみすむ
1
第一章の現今の大学システムに対する作者の慷概は正直どうでもよかった。市場制度を導入することで競争が生まれてサービスは向上するから、大学を企業に準えて生徒を「お客さま」扱いするという意見には同意し兼ねる。日本の医療は、市場制度を導入して患者を「お客さま」扱いしたために現在崩壊の危機に瀕している。経済活動に直接関わっていない企業以外の組織体に、市場制度を安易に導入するのはやはり短絡的な考えだ。ただ、専攻の話など、将来を見据えて大学で何をどう学べばいいか、何を為すべきか、について考えるヒントを得るには役立った。2011/12/21
-
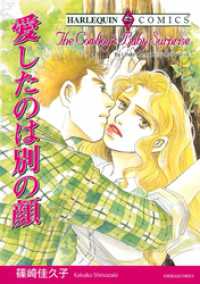
- 電子書籍
- 愛したのは別の顔【分冊】 5巻 ハーレ…
-

- 電子書籍
- BE BLUES!~青になれ~(38)…
-
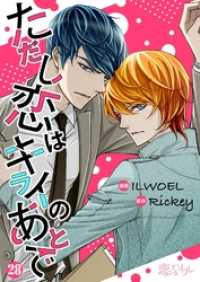
- 電子書籍
- ただし恋はキライのあとで(フルカラー)…
-

- 電子書籍
- 教育技術 小三・小四 2019年 7/…