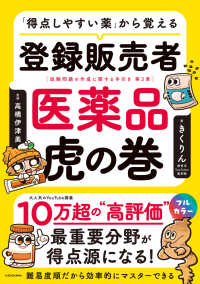内容説明
「クレオール主義」とは、なによりもまず、言語・民族・国家にたいする自明の帰属関係を解除し、それによって、自分という主体のなかに四つの方位、一日のあらゆる時間、四季、砂漠と密林と海とをひとしくよびこむこと――。混血の理念を実践し、複数の言葉を選択し、意志的な移民となることによってたちあらわれる冒険的ヴィジョンが、ここに精緻に描写される。「わたし」を世界に住まわせる新たな流儀を探りながら、思考の可能性を限りなく押し広げた、しなやかなる文化の混血主義宣言。一大センセーションを巻きおこした本編に、その後の思考の軌跡たる補遺を付した大幅増補版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
32
文化全般や政治にも切り込みつつ、それ以上に今福はこの本で「言葉」が持つ問題を丹念に分析する。1人の人間に内在する母語と、彼/彼女がしばしば翻弄されるまったくの外国語。自身の中でさえしっくりこないこともあるそんな諸言語の分裂状況をめぐって、今福は多彩な書籍の参照を主に表立ってはこれみよがしな世界情勢の分析に淫せず、しかし的確に個人がそうした多言語の状況下で引き裂かれうる現実を分析する。その帰結が今福が依拠するポストコロニアリズムであり「クレオール主義」なのだろう。だが、それは「ぼくたち」の問題でもあるはずだ2024/07/21
踊る猫
28
流石に引用される本や話題は古びているが、しかし論考自体は未だアクチュアルで読ませる。現代の古典と呼ぶべき本だろう。今福龍太の論考は読んでいて元気が出る。それは彼がポジティヴにそしてアグレッシヴに本を読み、文化を参照し、そこから柔軟に越境して様々な思想家や文学者を繋いでテクスト・ジョッキー(上野俊哉)として流麗にミックスするからだろう。言うなれば今福龍太には過度に自己主張して俺が俺がと迫るだけの自己が存在しない。自分がない、というか希薄なのだ。それ故にどんな対象にも素直に己を溶け込ませ同調させる美徳を備える2020/09/04
zumi
24
最っっっ高... 冒頭と締めはアツく、論旨はクールに。世界文学を読む上で、というか人生において必携の一冊。自明と思っている帰属を吹き飛ばし、絶えず揺れ動くアイデンティティを追求していく。それは他者と自己の関係を往還し、大地へと主体を溶け込ませるながらも、移動し続けることで、「越境」という行為が、あらゆる文化から解き放たれた自由を孕む風景を呈するであろう。彼らの世界は、限りなく混沌に接しながらも、光り輝く独創的な知を創出し続けるほど、あまりにも力強い。「ここではない何処かへと到達するための生」を目指して。2014/07/10
スミス市松
22
本書が上梓された十年後、ハイジャックされた二機の大型旅客機によって「クレオール」という名の楽園、虹色に輝くバベルの塔は瓦解したように思われた。しかし現在、その瓦礫を滋養にして生まれた新たな文学が本書の謳う「主義」を受け継ぎつつある。ジュノ・ディアスやカレン・テイ・ヤマシタ、ダニエル・アラルコン、ハ・ジンなどの文化的混淆を背景に持つ新しい英語圏の作家たちがごく自然に「クレオール主義」に則った小説作品を書きはじめているのである。新たな世界文学を予感させるその嚆矢としても、本書は今まさに読み返されるべきだろう。2012/06/12
ハチアカデミー
18
A ドキュメンタリーとしての学問は可能かー 伝統的言語をブリコラージュし、自然発生的に生み出されるという、生成に矛盾をはらむ言語=クレオールをキーに、異文化が混じり合い、まさにいま生まれたトポスをめぐる思想的冒険。~とは何か、といった根源を問う視点からは見えない、必然も必要も偶然も入り交じる、グロテスクでシュールレアリスティックな文化を紐解く試み。非中央的文化の中で、かつてのような失われた人間のルーツを探るのではなく、アクチュアルな現場を目撃せんとする眼差しを持つこと、それが今福文化人類学なのだろう。2012/06/14
-
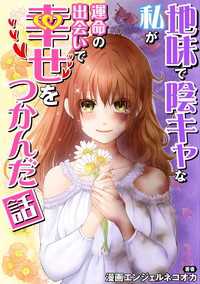
- 電子書籍
- 地味で陰キャな私が運命の出会いで幸せを…
-
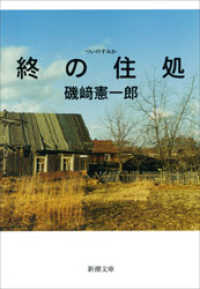
- 電子書籍
- 終の住処 新潮文庫