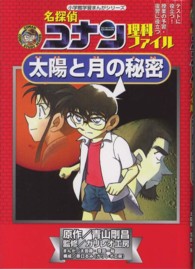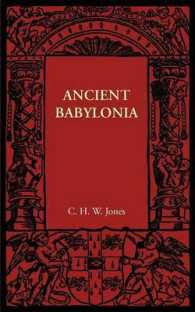内容説明
笑いにグローバルスタンダードはあるのか!?
壮大なテーマを大学教授とジャーナリストが追いかける!
「コマネチは世界通用するのか?」
「女性と男性、ユーモアセンスがいいのはどっち?」
「笑いは本当に『百薬の長』なのか?」
「日本の笑いは外国人にも理解できるか」
あらゆる角度、あらゆる場所でユーモアを掘り起こす、傑作ノンフィクション誕生!
この本は僕の海馬をおおいに刺激した。
――A・J・ジェイコブズ『聖書男』著者
二人は「何が人を笑わせるのか」をみごとに説明してくれた。
科学と、物語と、風刺と、ニットベストの完璧な合わせ技で。
――アダム・グラント『GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代』著者
笑いの仕組みを追い求めるすばらしい旅の物語だ。
――スーザン・ケイン『内向型人間の時代』著者
インディ・ジョーンズ的でもあり、ティナ・フェイ的でもあり、ときに『CSI:科学捜査班』をも思わせる。
――チップ・ハース『アイデアのちから』著者
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふ~@豆板醤
32
3。世界中を旅しながら各地の笑いを研究した本。大阪の吉本が日本代表なのは納得(笑)「「おもしろい人」になるには、一体何が必要なのか?」という疑問に始まる旅..!「世慣れていて博識なことも重要」「アウトサイダーであれ」「笑いは勢い」など、色々ヒントがあって意外とためになった。「笑いは逆境を乗り越える力をくれる」2017/10/17
遊々亭おさる
14
人はなぜ笑うのか?笑いを生むメカニズムを科学的に立証すべく世界各国の笑いを体験する旅に出た教授と記者の二人連れ、旅の最後は自らがスタンダップ・コメディの舞台に立ち研究の成果を披露すると言うがその結末や如何に?世界共通の笑いのツボは幼稚園児が喜びそうな下ネタだそう。でも、同系列に思えるダチョウ倶楽部のおでんネタのようなものはアメリカ人であるお二人にはピンとこなかったようで。笑いのツボは文化により左右されるんだなと。笑いは希望の灯火でもあるが差別を内包する厄介なもの。笑いの効用と暗黒面を理解して楽しい人生を。2016/04/22
Akito Yoshiue
4
終盤になるに従ってどんどん面白くなり、最後のほうは感動するシーンもある。2015/07/15
Masaaki Kawai
3
なぜ笑うのかを研究する教授とジャーナリストが世界を旅する道中記。タンザニア、日本、デンマーク、イスラエル、アマゾン、色んな所で笑いについて考えられました。そして、ハッピーな締めくくり。思ってた以上に楽しい本やった。しかし、この本を読み終わったからといっておもしろくはなりません。2015/07/21
牙魔
1
「笑い」を科学的に分析するなんて無謀では?と思いつつ。最初の米国ではスタンダップコメディとシュールギャグの研究。いかにもアメリカ。アフリカでは笑い病(ちょっと不安に)、生き物としての笑いがテーマ。日本では文化の違いによる笑いの壁を体験。北欧では宗教と笑い、パレスチナでは極限状態と笑い、アマゾンでは健康と笑い。読み終わってみるとそれぞれ納得できるオチではあった。2021/07/19
-

- 電子書籍
- パパと奏でるEVERYDAY 5 ズズ…
-
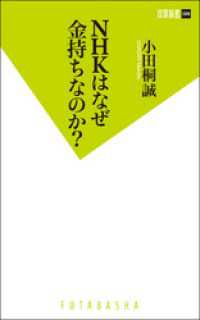
- 電子書籍
- NHKはなぜ金持ちなのか? 双葉新書