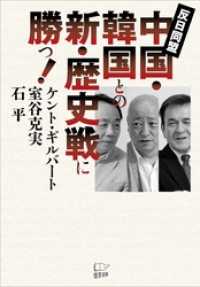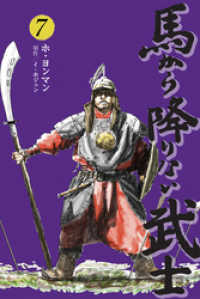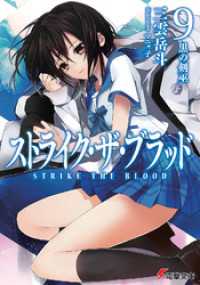- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
私たちはなぜこんな働き方をしているのか、いつまでこんな働き方を続けるのか。本書は、労働経済学の見地から、働くことにまつわる根本的な疑問を解き明かしていきます。日本型雇用のゆくえ、ブラック企業の根幹、これから失われる仕事の見抜き方……。働くことの基本を知り、いま起きていることを理解し、未来を考えるために必要なことを、具体的な事例に沿って解説します。これからの激変する社会で生きるための必読書です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
84
NHK Eテレ(毎週水曜 22:00)の「オイコノミア」を文字起こしした感じかな。まさに「働き方の経済学」。又吉さんとの対談を載せてみたら、さらに面白くなったかもしれないw2016/05/17
きいち
31
平易に、プレーンに、働くということの現在を解説。立場によって「こうあるべき」理想が必然的に変わってしまう分野で、そんな風に記述していくためにかなり丁寧に注意されていて、これから働く人や今の自分の働き方以外知らない人にとってとても役に立つものになっている。◇一方で唯一強調される「べき」は、働く者は(使う者ももちろん)これら仕組みや制度、将来像は必ず知っておかねばならないということ。知ることは力であるだけではなく、世の中の一員としての義務なのだ。◇これは、反知性主義との闘いで一番勝算のあるやり方かもしれない。2015/05/06
犬こ
23
高度経済成長期に形成された雇用慣行や法制度が、時代の変化によって実態に合わなくなりつつある昨今、働き方の方向性を常に知っていく意識が必要とのこと納得です。労働法、経済についてとても分かりやすくまとまった一冊。2017/07/30
けんとまん1007
19
解っているようで解っていないのがこれ。働き方について。世の中の制度だけでなく、最近の傾向、今後の見込みなども含め、いろいろな観点から述べられている。そして、大上段に構えた視点ではなく、あくまでも、一人の人として淡々と述べられているのがいい。そのおかげもあってか、随分と身近なこととして受け取ることができる。この本をきっかけとして、自分なりに関心のあるところを深堀していけばいいのだと思う。そんなインデックスにもなる。2016/05/21
Mc6ρ助
14
働くもの、必携の教科書。よく出来ている。著者の予測『働き方の未来(⑭) 社会保障については、企業ではなく国の責任で行われることが次第に明確化され、直接的に行われるようになるでしょう。(p172)』「自助、共助、公助、そして絆」という現政権との隙間の奈落に落とされてしまう多くの労働者、働くことに自覚的にならねばとは思うが、いつも会社に厳し過ぎるかも知れないけれど、お金持ちにはノブレス・オブリージュと主張したい爺さまでした。2021/06/02