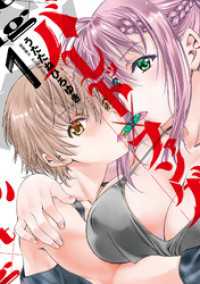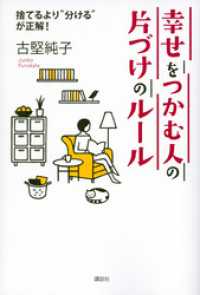内容説明
塩害に強い綿」を津波被害を受けた宮城県沿岸部の農地で栽培し、とれたコットンを国内で紡績して服やタオルを作り、販売する「東北コットンプロジェクト」。
東日本大震災直後に東京や大阪のアパレル企業が提案し、宮城県沿岸部の農家とともに綿花栽培に取り組みました。18団体で始まったプロジェクトは、現在80社以上が参加、地域や地元企業、学校などにも活動がひろがっています。
復興支援、農業の6次産業化、エシカル消費など、いま日本が向き合う課題に取り組むプロジェクトの3年間の記録を、そこから見えてきた日本の綿花栽培の歴史、現在の綿花事情とそこにはらむ問題なども交えまとめた1冊です。
目次
プロローグ
1章 東北で、綿をつくろう
はじまりのまえ
始動
コラム:綿とは 特徴と歴史
2章 種から綿へ「農」
荒浜と綿花/名取と綿花
コラム:日本の綿花栽培
3章 綿から服へ「商・工」
綿が服になるまで/東北コットンの届け方
コラム:これからのコットン
4章 綿から広がる
東松島と綿花/地域へ、子どもたちへ/コットンから考える
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chietaro
2
津波・原発事故の被害が大きく取り上げられる東日本大震災だけど、津波による塩害も忘れてはいけないです。そこに綿花を植えようという取り組みが、農家や企業だけではなく地域や教育にも輪が広がるのが面白いです。復興の一つの道として知ることができて良かったです。2018/02/12
osakaspy
2
強いメッセージを感じるわけでもないし、感動するわけでもないが、何かをしなくちゃいけないと思わせる力のある本。綿のように軽く心に囁いてくる、おこがましくない感じが楽に読ましてくれた2014/08/22
Kuniaki Hanatani
0
JALの機内誌でプロジェクトは知っていたが、最近宮城に転勤になったので読んでみた。 まだマネタイズまでは至ってなさそうだが、地産地消、自給自足は重要だと痛感した。綿が100%輸入に頼っているのに驚いたのと外向的にやばいよねと思った。 こういうプロジェクトはいつの間にか自然消滅してることが多いけど何とか継続して6次産業を確立してください。2021/06/07