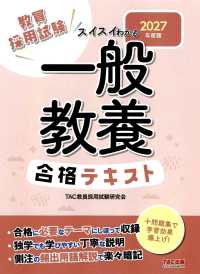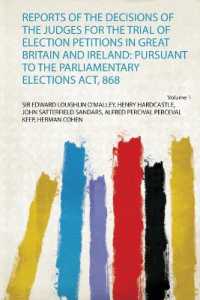内容説明
英語を理解するということは、単に単語を覚えればいいのではなく、英語ネイティブたちの頭の中にある、英語によって切り取られた世界の成り立ち、そのイメージを捉える必要がある。他言語に比べても、英語の世界観と日本語の世界観の間には、乖離がある。本書では英語の世界観、英語ネイティブの思考方法について考え、その先で、英文法の原理を探り、動詞、名詞、前置詞などの根本的な役割について、とことん平易に説明する。(講談社学術文庫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mr.チャーリー
54
なんで、ここでatじゃなくてinを使うんだろう? mustとhave toの使い分けは? 学校では決まり文句だから覚えなさい的に授業が進められた記憶がけっこうあったように思います。 今になって本書を読んでモヤモヤがスッキリしたことが少なくありません。著者は、もともと日本語と英語は相性が悪いんだという話から始めます。要するに英語のどの辺が日本人にはわかりにくいのか?なんとなく漠然と感じている英語への違和感の原因を考えます。 これから英語に再度チャレンジしようという動機付けの一冊になりました。 2017/06/09
弥勒
17
すごく刺激的で面白かつた。といふのも、私自身、最近気になつていたことだからです。高校生の頃英語が得意ではあつたが、それは単に覚えるのが得意であつただけで、英語の本質的な理解をしていた訳ではないことに気付かされたのです。本書では、英語は日本人にとつて非常にイメージのし辛い言語であるが、第二言語を学ぶ意義は母国語を対象化できることにあると、説かれてをり、その通りだろうなとしみじみ感じました。最近、英語と日本語のことで非常に悩んでをり、英語学習をとめてゐたので、これを機に再開しようと決意を新たにしました。2015/10/18
中年サラリーマン
17
使用言語が世界観を規定する。日本語でものを考えるということは、前提として世界がすでにあるということ。その世界に存在する個々のものの関係性に気をつけて構造を組み立てていくのが日本語で考えるということ。関係性重視なので視点は目まぐるしく入れ替わる。英語は逆だ。何もない真空にポンっと主語をおくことができる。そして、主語が何かに働きかける。いろいろなものに働きかけ主語の周りにどんどんと世界を広げていく。ベクトルが日本語と逆なのだ。日本人の気質、そしてアメリカ人の個人主義は言語も関係しているのでないかと著者は語る。2015/03/22
RmB
9
日本人が英語を学び、アメリカ人が日本語を学ぶ。日米同盟強化に必要なことだと思います。安倍首相はそんなこと考えてないでしょうけどね。2015/05/15
たか
8
これは良書です。英語が得意、苦手にかかわらず一読の価値あり。2015/07/09
-

- 和書
- 動物のことばがわかる本