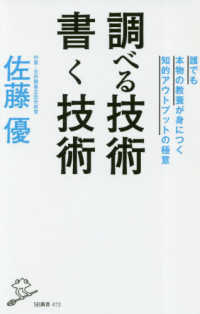内容説明
中世の村はひたすら明るかったのか。あるいは村の隅々にまで戦国大名の支配が浸透していたのか――実態は「自力」のさまざまな発動が織りなされる熟した社会であった。村同士の争い事の際の言葉戦いという挑戦の作法、暴力の回帰や反復を避けるための人質・わびごとの作法、また犯罪解決のための自検断の作法などを検証し、中世の村の実相に迫る。(講談社学術文庫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
無重力蜜柑
11
近現代史が専門の自分は中世史に関する本を読むといつも、限られた史料から大胆に推論を展開していく方法論に驚かされる。本書は中世史の中でも庶民の風俗や慣習に焦点を当てた社会史なので、台帳などの細々とした記述から民俗学などの概念で論を展開していてかなり異様だった。第一部「挑戦・身代わり・降参の作法」、第二部「村の武力と自検断」は面白かったが、第三部「庄屋・政所・在地領主」は専門用語と史料からの引用が多すぎて微妙だった印象。ただまあ、自分は近代史の方が面白く感じるなと。2024/06/30
in medio tutissimus ibis.
5
とにかく話が具体的すぎるのが、研究としては堅実さなのだろうけれど、読み物としては読みにくい。とはいえ、具体的だからこそ、時間を隔てた全く異なる文化についてよりリアルな理解ができたようにも思う。戦国時代の村民は、今日的な視点から見るとお百姓さんという感じに見えてしまうのだけど、勿論武装していたのだし(だから刀狩りとかあった)、弓箭の道が出てきたり、血の気の多い戦闘集団としての若衆を抱えていたりと、もっと獰猛で自律的な存在だったのだ。一方で落とし前の為の浪人を養っていたり『七人の侍』なんかよりももっと逞しい。2018/11/12
sfこと古谷俊一
3
中世近畿の村落関連史料をもとに、村の紛争解決手法やを領主との関係を検討する。犯人は殺せ、投票で気に入らないのを殺せ、となるあたり、実にこう共同体の私刑は今も昔も変わらんなあと思ったり。2008/11/06
眉毛ごもら
2
村々の強かさやら領主とのやり取り重層化している村の組織年貢の値引き交渉、交渉のための人質や村のために死んでくれたらあとのもんは世話するから!という生贄並みのエゲツない制度など大変興味深いものがいっぱい。大河の直虎のときに採用されてた話も多かったので懐かしい。解死人とか。お寺さんでも盗人や犯罪者は指名手配賞金付きで処刑ってあってエエエっと思ったけど冷静に考えたら日本の僧侶って血の気が多かったなと比叡山の方を見ながら。徳川期の五人組とかの源流はすでに出来てたのではレベルで連帯責任が重いので凄いなと思ったり。2022/09/08
かやは
2
資料として。身代わりを立てられるとか、意外と抜け道があって面白かった。これを読んだ後「七人の侍」を観ると印象ががらりと変わりますね。百姓はもっと強くて強かだったんだ、みたいな。2012/09/10
-

- 電子書籍
- テレワークで働き方が変わる! テレワー…