内容説明
近代の名著として名高い『茶の本』は、明治39年(1906)に岡倉天心(1863~1913)が英語で書きアメリカで出版した書物です。そのタイトルや、再編集された利休の逸話・切腹話が多いことから、「茶道」について説きおこした本とも思われがちですが、実は、ハラキリで欧米に認知されていた当時の日本人を、日本の文化を擁護するために、欧米でも飲まれている「茶(紅茶)」を引き合いに出し、理解を求める意向で執筆されたものでした。七章からなる本文は短いものですが、どう解釈するかは訳者に負うところが大きい書でもあります。今回は、茶の道学実を兼ね備えた筆者が原文に挑んだ、茶の湯関係者待望の一冊です。
今回の新訳では、「茶道Teaism」と「茶の湯 tea ceremony」を明確に訳し分け、「道家思想Taoism」「禅道Zennism」と対置させるとともに、「茶道は、道教の仮の姿であった」と書いた天心の深意にせまっています。
また、英文のパラグラフごとに小見出しをつけているのも、訳者の工夫です。
60ページにおよぶ解説と、岡倉天心略年譜付き。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
お萩
5
どれから読んだら良いか分からずさらりと読めそうなもので概要を掴もうとしてみる。道教の話の辺りで「あれこれお茶の本ではなかっただろうか」と目が泳ぎ、花御供の章で「花によっては死を誇りとするものもある」などと書かれてはもう。恐ろしい世界を覗いてしまった気持ち。不完全なるモノへの崇拝と儚い試みが茶道。(…という事を理解するにはまだまだ遠くて…)2016/11/29
Tomoko 英会話講師&翻訳者
2
岡倉天心が西洋に伝えようとしていたことはどんな事なのか興味があって読んでみた。さらりと読めるけど深い深い茶の世界。書いてあることを理解するには、もっと日本のことを学ばなきゃ。「利休の最後の茶」p.141~2015/10/21
amabiko
1
いろんな日本語訳があるが、本書の訳は非常に明晰。段落ごとの小見出しも、難解な原書の理解を助ける。Teaismとtea-ceremonyの使い分け、肝となる概念の一つthe Unsymmetricalの訳語「数奇」についてなど、60pにおよぶ詳細な解説も明解。2013/09/22
-
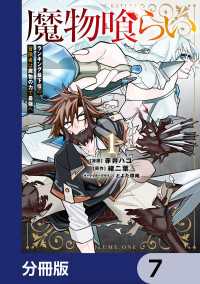
- 電子書籍
- 魔物喰らい【分冊版】 7 電撃コミック…
-
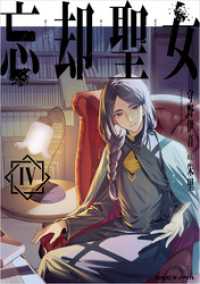
- 電子書籍
- 忘却聖女 4巻 SQEXノベル
-
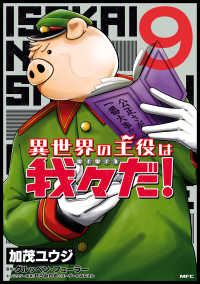
- 電子書籍
- 異世界の主役は我々だ! 9 MFC
-
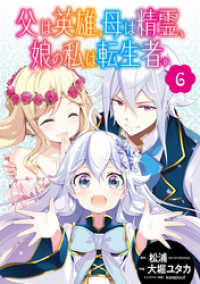
- 電子書籍
- 父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。【…
-

- 電子書籍
- 義風堂々!! 疾風の軍師 -黒田官兵衛…




