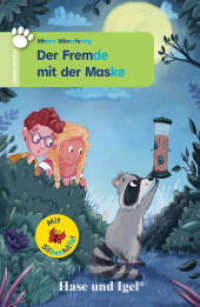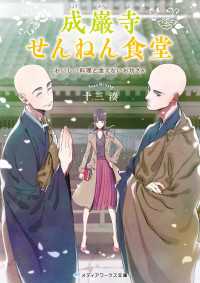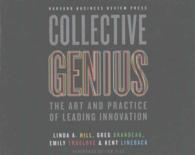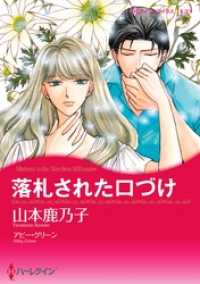内容説明
国家の繁栄には貿易の拡大を必要とし、それにはシーレーン確保や海軍力増強が重要となる――。近代海軍の父・マハンの海上権力理論は、秋山真之をはじめとする旧日本海軍のみならず、同時代の列強、そして現代に到るまで諸国家の戦略に多大な影響を与えている。海の可能性が注目される今、大きな示唆を秘めた海洋戦略論を、代表作を通して紹介する。(講談社学術文庫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちぃ
34
抄訳部分を読んでから序文に戻るのがいいかもしれない。マハンの論はかなり好戦的で「やられる前にやれ」「攻撃こそが最大の防御」と言わんばかりである。私は日本人なので台頭する日中に対する警戒心のこもったマハンの視点はなんとなく新鮮に映った。これまで「民衆⇔権力⇔戦争」の三者間に対する知識は蓄えてきたと思うけれど『権力⇔権力』の関係性にはいまいち関心が薄かったのだなと反省。中世までの戦史と地政学についてもっと勉強したいなと思った。当時の日本人の知への貪欲さを見習いたいが、捉われて現実を見失うことないようにしたい。2017/02/19
植田 和昭
14
読んでいて頭がおかしくなるかと思った。マハンと言えば秋山真之が師と仰いだ人物。海上権力史といえばアメリカの海軍兵学校のみならず海上自衛隊でもバイブルとされている書物。しかし、内容はと言えば西洋第一主義、キリスト教第一主義、アメリカファーストの書である。彼は自分の言葉に酔いしれている。日本で言うと石原完繭の最終戦争論が近い。述べられているのは限りない東洋文明への侮蔑、偏執狂的な誇大妄想。支離滅裂な論法。彼が、少将でやめなければならなかったのもわかる気がする。これは、狂人の書である。2024/09/08
白義
14
シーパワー論の基礎を集成したマハンの思想を、さまざまな論文から浮き彫りにする入門アンソロジー。通商圏の拡大とそれを保護、維持するための海軍力。さらにその海軍力を円滑に働かせるための根拠地の三支柱からなる海上権力、という連鎖的な考え方が分かりやすくまとめられている。時評でも、太平洋の制海権を握るための、ハワイや対中国問題の重要性を19世紀末から盛んに論じている先見性には、そのイデオロギー性や荒い文明論的枠組みを考慮してもなお驚かされる。帝国主義時代が前提の理論だが、現代でも基本は妥当する2014/06/28
西郷さん
10
前々からマハンに興味があったので読んでみました。多分、最初の訳者の解説が無かったら完璧に詰んでいたと思います。マハンって日本ではあまり知られていませんが、彼の論文を読んでみると、何でマハンが歴史の教科書に載らないのか不思議でなりません。マハンのように広い視野を持ち、素直に物事を見ることは見習いたいですね。2014/02/09
newborn
4
マハンの影響力で日本を含め、西欧の海軍も改革されていったという序盤の記述がありましたが、彼の主張を読んでみると当たり前の事を言っているようにしか個人的には感じませんでした。彼の理論によってどのようなアイデアを諸国が持つようになったのか時代背景の知識がないもので、どこが革新的だったのか全然分かりません。現代の社会システム論とか世界構造の学問と比べると見劣りしてしまうような、単純な世界観が目立ちました。2015/03/21