内容説明
大震災後に歩む、芭蕉の「みちのく」
松尾芭蕉の『おくのほそ道』は単なる紀行文ではなく、周到に構成され、虚実が入り交じる文学作品である。東日本大震災の被災地とも重なる芭蕉の旅の道行きをたどり、「かるみ」を獲得するに至るまでの思考の痕跡を探る。ブックス特別章として、芭蕉による『おくのほそ道』全文を収載。
[内容]
はじめに―『おくのほそ道』への旅
第1章 心の世界を開く
第2章 時の無常を知る
第3章 宇宙と出会う
第4章 別れを越えて
ブックス特別章 『おくのほそ道』全文
松尾芭蕉 略年譜
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Y2K☮
30
「古池や蛙飛び込む水の音」誰もが知っている芭蕉の句。だがその真の価値を誰も知らない。学校で教わった? そんな記憶はない。もし本書を読まなかったら、知ったつもりの己に疑問すら抱かず一生を終えていたのか。「不易流行」は間違いなく禅に通ずる思想、というか禅そのもの。変わらぬものと変わるものは相反する存在ではなくひとつ。一元論。何物にも囚われぬ生き方がすなわち「かるみ」の境地だ。人間も世の中も変わり続けるようで変わらない。進歩のなさに絶望するのではなく、その軛から己を解き放つ。執着せず期待せず、ただ真理に遊ぼう。2022/02/19
ほよじー
15
★★★★芭蕉はおくのほそ道で不易流行とかるみという2つの考え方を掴んだ。不易流行とは、宇宙は絶えず変化(流行)しながらも不変(不易)であるという壮大な宇宙観であり、時の流れとともに花や鳥も移ろい、人も生まれて死んでゆくという自然観でもあり人生観でもある。かるみは不易流行という認識の上に立った人生の生き方、行動論であり、様々な嘆きに満ちた人生を微笑みをもって(軽々と)乗り越えて行くというたくましい生き方。2018/05/16
けせらせら
9
なぜ松尾芭蕉が特別なのかが少しわかった。 後半に、おくのほそ道 の本文が載っていた。2022/12/22
しおり
9
江戸時代の作品だけどさすがに古文。中々読み進められなかった。言葉遊びだった俳句に「古池や」と心の句を入れることに成功したことが芭蕉のすごさ。蕉風開眼の句と言われていた意味が分かった。白川の関までは旅のための禊の意味合いが強い。そして歌枕を探し始める。歌枕の実物が見れると期待が膨らんだ芭蕉だったけどその期待が裏切られることも多かった。時が経ちすぎていてもう風化していた。でも松島は綺麗だったらしい。平泉あたりで不易流行に至ったのかな?不易と流行は両立する。流行の中でもそのまま生きることが「かるみ」だと思った2021/02/28
takakomama
8
「月日は白代の過客にして~」出だしだけ知っている「おくのほそ道」 東京を出発して歌枕を訪ねてみちのくへ、北陸を経て大垣までの長旅は健脚ですね。俳句の完成者である芭蕉のどこがどうすごいのかが、よくわかりました。俳句の17文字に現実と心情が凝縮されています。一つの言葉にふたつの意味をかけ合わせていたりして奥が深いです。不易流行、悲しみや苦しみが多い世界を、軽々と生きていきたいものです。先日、草加の芭蕉ゆかりの地に行ったのも何かの縁かもしれません。伊集院光さんの「名著の話」を読む前に予習。2023/06/29
-
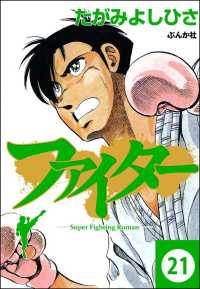
- 電子書籍
- ファイター(分冊版) 【第21話】
-

- 電子書籍
- 教育幻想 ──クールティーチャー宣言 …







