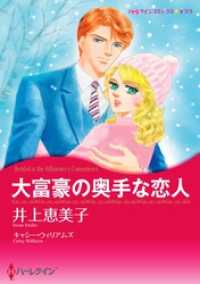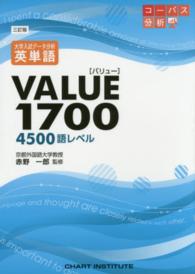- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
情報は、検索するな、覚えるな、整理しすぎるな。問題意識を持ち、アナログな情報に触れれば、アイデアや仮説が生まれる。『仮説思考』の著者であるトップコンサルタントが明かす、独自の思考法・発想術。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ほよじー
11
★★★「仮説思考」の著者による右脳発想法。日ごろ私生活でやっているアナログな情報収集やひらめきをビジネスにも活用すべきと言っている。この本が出たのは2008年末。今では私生活にもiPhone等を使ったデジタルな情報収集が一般的になって来ている。問題はデジタル情報をいかにヒラメキに活用するか?アイデアを生む、閃く、スパークするにはデジタルよりもアナログが良いという著者の意見はもっともだと思う。ネット検索だけでは差別化できない。2014/01/28
デビっちん
10
再読。ひらめきには、きょろきょろする好奇心が大事。スパークに必要なのは、問題意識と自分なりのデータベース。なぜ?なぜ?なぜ?ちょっと待て。問題意識を持ったら、一度手放す。一度問題を脳が認識したら、関連する情報に接すると、脳がその情報を自然と引っかけ、自分のデータベースと化学反応を引き起こす。アウトプットする最終段階までは、型にはまりがちなデジタルのツールよりも、自由で気ままなアナログの手法が良い。自然と情報が引っかかるように、潜在意識と仲良くしておこう。そのために、あれとあれを継続していこう。2015/09/10
naotan
8
『戦略読書日記』から。著者の言う右脳と左脳の話は、楠木建氏の抽象と具体の関係に似ていると思った。連携が大事。2017/02/23
デビっちん
8
この本のテーマは、日ごろの私生活で自然と行っているクリエイティブな発想や行動を、仕事にも取り入れようという内容。問題意識がスパークを生む。集めた情報は整理せず、覚えるようとしない。チェックした情報が、脳の中で混ざり合い、何か新しい情報とふれ合うことですぐにスパークしたり、熟成してからだったりする。集める情報は現場での一次情報が良い。誰でも手に入れられる情報では、面白いアウトプットはできない。公私混同することで、新たな発想が生まれてくる。ロジカルシンキングに代表される左脳でけでなく、イメージの右脳を活用する2014/10/20
Yohei
7
★★★★☆コンサルタントにしては、ひらめきの類を重視した珍しい書。巷にあふれる『仕事のできる方法』とは実は、仕事ではなく、『作業のできる人間になるための方法』でしかない。イノベーションは整理術やロジカルシンキングといった作業効率を高める左脳だけでなく、一見ルーズな右脳によって常識を離れ、情報を熟成させ頭の中のデータベースと自由に化学反応を起こさせるか、その過程を左脳によって邪魔しないことができるかが勝負。2015/09/29