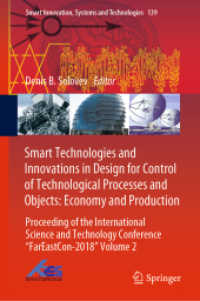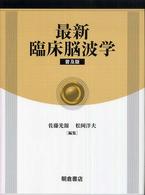内容説明
昭和37年。三等機関士の関本源蔵は妻子を陸地に残して北洋漁業に出立した。航海の途中で大時化に襲われた源蔵は、戦時中にサイパンで別れた父親と、アメリカの潜水艦に撃沈された船に乗っていた幼い友のことを思い出した――。生還は果たせるのか? 生きて働くことの意味を激しく問う「昭和の海の男」の物語。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolgang1957
30
南氷洋捕鯨の描写が大迫力で凄かった( ̄◇ ̄;) 現在では、どうなってるのかな?禁止される前に続編出してもらえませんか^^; ...お父さんとして読んだら反省点ばっかり頭をよぎるけど、ぼくやったらあっと言う間に氷の下やろねぇ(´・_・`)やっぱり反省しよm(_ _)m2014/12/25
James Hayashi
24
源蔵が乗っているのは漁船であるが、漁師としてではなく機関士として。冬の厳しさの中、時化のなかなど海の大きさと怖さ、また一度港を出ると誰が死のうとも港へ帰れない男の世界をまざまざ見せる。会社に属する源蔵は鯨漁船にも乗り込み南氷洋に向かう。支えている家族は長期不在にしている為特に子供と疎遠になる。書かれている状況は海の上であるが、源蔵が若者に語る仕事に対する態度は心を打つ。職に対し選択権があるためか不平不満を思う自分に再考を促す。爽やかな感動も味わえた良作。2015/04/29
lily
8
「海の男」として船上で働く機関士と家族の物語。前半の船舶用語が飛び交う流れは正直流し読みだったが、後半の遭難シーンはハラハラして一気読み。昭和の武骨な漁師とその帰りを甲斐甲斐しく待つ妻という古き良き世界観だが、子供との接し方に悩むのは古今東西同じ。「世の中にかっこいい仕事なんてありはしない。傍目には華やかに見えても地味なものだし、着実に繰り返さないことには成果は得られない。」給料の多寡ではなく、どんな仕事でもコツコツやり遂げる後姿を見せることが、親が見せられる子供への何よりの「羅針」である。2020/12/08
キューカンバー
8
楡周平の秀作。ラストシーンの父と子の描写がこの作品を素晴らしい人間ドラマに昇華している。2016/10/11
hiyu
7
子どもの頃にはクジラが食卓に出ていた。その頃はこういう苦労があるとは到底思いつかなかった。敏雄は自分自身の姿であり、息子でもあったのかなあ。このタイトルに納得がいった反面、だとすれば、ラストにかけての描写と比すると、もう少し何かあってもよかったような気もする。2019/03/02
-

- 電子書籍
- 竜の秘宝を抱く乙女 2【分冊】 9巻 …