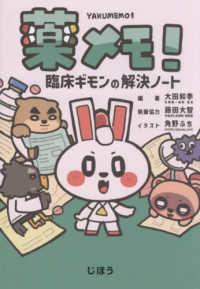内容説明
世界でいちばん短い詩――俳句。日本独特の短詩型文学における、主として切字の考察を通して日本語の豊かさを実証し、「省略の詩学」としての魅力をも解明する日本語論の先駆的名著。
-
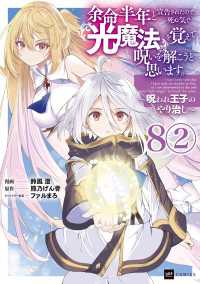
- 電子書籍
- 【単話版】余命半年と宣告されたので、死…
-
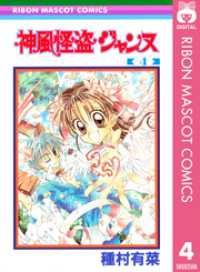
- 電子書籍
- 神風怪盗ジャンヌ モノクロ版 4 りぼ…
-
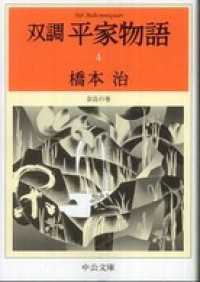
- 電子書籍
- 双調平家物語4 奈良の巻 中公文庫
-
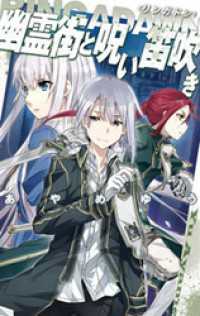
- 電子書籍
- RINGADAWN 幽霊街と呪い笛吹き…