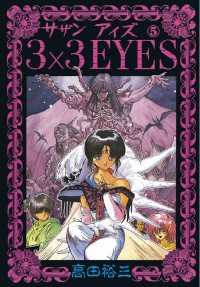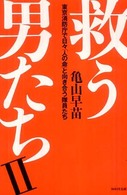内容説明
かつて一世を風靡しながらも、正史の陰に隠れてしまった「劇画」の流れ。その中心人物・辰巳ヨシヒロはなぜ劇画を描き、それが近年海外で高く評価されているのか。あの神様・手塚治虫ですら嫉妬するほどの才能をもち、海外で高く評価されている「TATSUMI」の半生を綴った衝撃の自伝!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
keroppi
67
劇画家・辰巳ヨシヒロの自伝エッセイ。「劇画漂流」は、昭和35年の日米安保闘争で終わっていたが、この本では、その後も語られる。印象的なのは、手塚治虫との話。手塚治虫が文春漫画賞の受賞パーティーにトキワ荘のメンツは呼ばず劇画家たちを呼んでいたとか、辰巳と共にフランスに旅したとか。解説で大塚英志も書いているが「置き去りにした子供たち」を手塚が気にかけていたことが分かる。手塚のこんな一面を初めて知った気がする。「トキワ荘史観」ではない日本マンガ史を見る。「劇画漂流」にはないエピソードもある。2025/09/11
arnie ozawa
2
劇画の第一人者というか、劇画という言葉の生みの親、辰巳ヨシヒロの半生記。特に貸本漫画の時代について詳細に記載されていたのが興味深かった。著者は当初大阪在住だったから東京でどのように貸本漫画が成り立ったかについては書かれていないので、そのあたりもどこかで読んでみたい。2019/03/10
Katsuto Yoshinaga
2
漫画家を志し劇画家となった著者の自伝だけに、漫画史、職業としての漫画家の生活ぶり、収入(原稿料)に関するくだり、同年代の作家との交流から窺える他の作家の性格等々が、拙い文章ながら、リアルに描かれている。以前から、かなりの数の10代でデビューした漫画家が、そんな年齢やキャリアでよく作品が描けるものだなと疑問に思っていた。画才はさておき、著者が映画や書物にもよく親しみ、表現等に関して他の作家と議論するシーンが垣間見られ、なんとなく疑問が解消された。時折、他の作家や出版社をディスるところもニヤリとさせられる。2015/01/09
ヤマダ キヨシ
0
☆☆☆☆2015/11/18



![お笑い芸人と学ぶSDGsババぬきカードゲーム [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47743/4774333050.jpg)