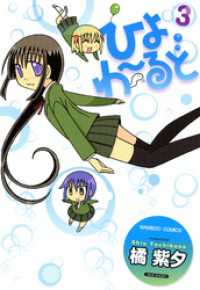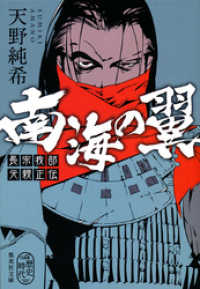- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
財政難のあおりを受け,また,国の度重なる政策変更によって翻弄される保育政策.待機児童問題は依然,深刻であり,幼児をめぐる環境は厳しさを増すばかり.しかし,その間も子どもは成長する.この「待ったなし」の問題において,私たちは何を優先すべきなのか.乳幼児期保育・教育の現状を歴史の中から見直し,ありうべき保育像を模索する.
目次
目 次
序 章 社会のまなざしを乳幼児期へ向ける
第1章 保育はいま
第2章 実際の姿を見つめる
第3章 保育実践の輝き
第4章 「子ども・子育て支援新制度」のスタート
第5章 子どもを社会が育てるために
あとがき
主な引用・参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
218
保育と何かというテーマに沿って現場の保育所から、制度の変遷についても勉強出来た。昔はそこらじゅうで遊んでたなぁと思い出した。2019/08/31
ゆう。
16
ストレートな題名に著者の思いを感じます。保育に対する良心的な入門書だとも思います。多くの人が手に取って読んでほしいと思いました。著者はこの本で「子どもを社会が育てる」意味を問い続け、保育実践の豊かさを述べています。そして、「子ども・子育て新制度」についても、子ども・親・保育者の視点から批判・建設的意見をしていく必要性を述べています。少し疑問だったのが、あとがきで保育園の設置主体と保育の質はわけて論じるべきだと述べているところ。設置主体が市場化・営利化されると質にも重要な影響を与えるのでは?と思いました。2014/11/03
2ndkt
11
「乳幼児期は、長い人生のスタートライン。しかし乳幼児期のことが社会全体の課題として受け止められないのはなぜか」という問いから始まる。著者は、「子どもを社会が育てる」と考えるべきだと訴え、そのためには「1、親を、社会全体の力で支える」「2、子どもがおもいっきり遊べるよう大人たちが保障する努力を重ねる」「3、保育者への応援」が鍵であると指摘している。2015年4月から、新しい「子ども・子育て支援制度」が始まる。本書が、新制度開始を前に出版されたのは意義深い。この本を通して、社会的議論が深まることを願う。2014/11/03
melon
10
命を預かる責任重き役目。2014/11/04
コーヒー牛乳
9
簡潔でストレートな問いだが、答えは言葉に詰まる。子育てとも子守りとも違う。安全や食事が確保されても、心が育っていなければ保育ではないとも思う。では何か?月並みだが、「人を育てる」ことだと思う。人は心と体でできていて、その両方を育まなければならない。とすると、人間として大事にしなければならない心とは具体的に何か?しっかりした哲学を持たないと答えられないなと思った。社会全体としては、保育所は「誰一人取り残さない」という意義があるとしみじみ思う。いろんな親と子、その誰もが支援を受けられるべき。2023/11/09