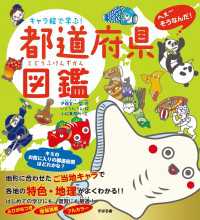内容説明
存在が荒々しく立ち現れると同時に隠蔽され忘却されていった古代ギリシャ以来、存在把握は劇的に変動し、現在、忘却の彼方に明滅するものとしてのみ存在は現前する──。存在論の歴史を解体・破壊し、根源的な存在の経験を取り戻すべく構想された『存在と時間』の成立過程を追い、「在る」ことを捉えようとした、ハイデガーの思想の精髄に迫る。(講談社学術文庫)
目次
まえがき
序 章 ギリシャの旅
第一章 カトリックの庇護の中で
1 荒地の中の教会塔
2 学寮の寄宿生
3 反モダニズムに伍して
4 哲学者の誕生
第二章 葛藤と模索
1 生業としての学問
2 スコラ研究にことよせて
3 明かしえぬ本心
4 大聖堂に背を向けて
5 自由とその代償
6 事実的な生と歴史性
第三章 雌伏の時代
1 アリストテレス論の構想
2 存在史の萌芽
3 ヘッセンの新天地
4 講義の中の時間論
第四章 『存在と時間』
1 『存在と時間』の刊行
2 気遣いとしての人間(還元その一)
3 時間性と歴史性(還元その二)
4 歴史を語る二つの視点
5 伝統とその彼方
第五章 ナチズムへの加担と後年の思索
1 凱 旋
2 決断の時
3 壮大なヴィジョンの陰で
4 黄 昏
ハイデガー略年譜
主要著作ダイジェスト
キーワード解説
読書案内
原本あとがき
学術文庫版へのあとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
25
『存在と時間』までの前半生とナチス加担問題が取り上げられており、後期ハイデガーに大抵のひとが興味を示さないのであれば、著者の判断は理解できます。評伝は必然的に若き日のハイデガーを描きます。著者の意図は哲学者として優れたハイデガーではなく、優れた哲学者ハイデガーをつくった一方でナチス加担問題の批判を受けるようなそのバックグラウンドに、すなわち彼の人間味を浮かび上がらせることにあると読めます。4章の『存在と時間』では、「根源的な存在経験」と「隠ぺいと忘却の頽落」の反復される二重性は両者が一体となって生起してい2020/10/14
またの名
11
同じ学術文庫で不気味な笑みを浮かべる表紙の人物と同一とは思えない、写真の凛々しさ。「内在的な読解や実存主義的な解釈とは少し違った」路線による解説は、伝記的な側面が強いながらもハイデガーを読む上では確実に理解を深めてくれそうな興味深いエピソードをいくつも含む。保守的なカトリックの徒としての出発から論理学や数学にも熱心だった修養時代、フッサール、ヤスパース、アレント等とのワケあり交流関係、ベルクソンからの影響やドロイゼン、ベンヤミンとの比較も差し挟みつつ、黒ノート問題への言及を文庫版で追加したりと意外に濃い。2015/03/13
カイロス時間
7
「存在」という言葉に違和感はない。「時間」という言葉にも違和感はない。でも「存在と時間」という組み合わせには、どこか違和感がある。何故その二つが並ぶのか?どういう繋がりでその二つを並べることができるのか?ハイデガーが語ったその繋がりの意味を、本書は平明に語りなおす。現在の優位に着眼し、その批判から独自の時間解釈を得る箇所は爽快。死への先駆けに3つの時間すべてが詰め込まれるとは…!時熟は造語すぎて笑えるけど胸熱でもある。私たちは誰もが時熟している。それは存在の基本構造だから。存在の根底にあるのは時間なのだ。2020/10/17
カワサキゴロー🍺📚🐈🐴
3
存在についての思索が、「存在の時間」と未完成で行くところまでいった見立ては面白かった。 ちょうど今、「存在の時間」を再読中なのでガイド的にもなった。 高田珠樹さん翻訳版「存在と時間」を買うか迷っていたのでちょうど良かったかも。2025/08/30
camus
3
現象学、実存主義、ドイツ観念論をまとめ上げた難解な堅物というイメージを持って臨んだが、案外読みやすくまとまっていました。フッサール、ヤスパース、アーレントとの親交や、ベルクソン、ニーチェ、カント、アリストテレスから受けた影響も理解しやすかったです。思索や言説によって自分自身を変革し、自分の関わる世界を変革しようとするのが哲学者や宗教家、広く思想家と呼ばれる人々の人生の意義なんでしょうが、それは変化を望む過激派の求心力となり互いの化学反応を引き起こすのは必然なのかもしれません。今読まれるべき本だと思います。2017/02/15