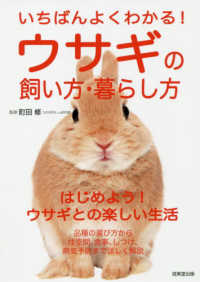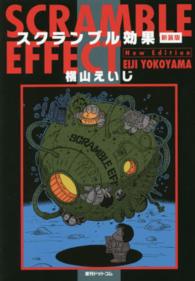内容説明
「自分のどこがいけないんだろう」――。ちょっとしたきっかけからいじめられるようになり、その呪縛から抜けられなくなる子どもたち。スマホを携え、SNSに常時アクセスする彼らにとって、いじめとは学校だけではなくネット上でも毎日24時間続くものであり、対策はますます難しくなっている。ジャーナリストである著者は、ティーンエイジャー3人の事例を徹底検証するほか、フェイスブック本社を取材し「ネットいじめ」の問題について探る。大人が子どもたちのためにできることを考える渾身のノンフィクション。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
詩歌
15
安易に正義と復讐に流れてしまう世論の恐怖。スマホ世代の、「常に闘って勝ち取る社会」で起きる「ドラマ」。この本が取り上げた件で、被告も原告も被害者になってしまい、得をしたのはメディアと地方検事というのがとても米国的。いじめや「ドラマ」を作りだす環境を変えようとする、子供自身の取り組みもある。本書に出てくる質問がとてもよくできていて、私も真似から初めたい。ダン・オルウェーズに興味をひかれたので、後で調べる為にメモ。2014/09/06
あお
10
いじめっこがどんな理由でいじめを始めるか、自分が知らないパターンが存在することが分かった。親からの虐待 友人のいじめ 鬱病からの苛立ち 仲間内でのポジションの確立etc。ニュースをみると勧善懲悪なストーリーが語られるだけでいじめっこの心理はみえてこないので私には貴重な知識だ。いじめは本能的なものかもしれない、病気のようなものかもしれない。私が重要だと感じたのは傍観者の存在。いじめっ子といじめられっ子は共に暴力の渦中にあり病んでいる。彼らを正しくみれる傍観者こそ、正しい行動を起こせる勇気を。2015/11/02
mari
10
子どもがどのようにネットでのいじめに巻き込まれていくのか?外国でのケーススタディについて書かれた本。子どもたちが使う前に、きちんとマナーや起こりうるトラブルについて、伝えていきたい。(子どもだけでなくて、親がネットいじめやっちゃってる場合もあるけどね。。)2014/09/23
ぱぴい
4
題名を読んでギクっとした。私たちの子ども時代にはなかった、スマホ世代のいじめ。もし、我が子がスマホを持たせることを考えたら、こういうことも視野に入れなければならないな、という親としての思い。教師としてこの話題に関する引き出しを増やさなければという使命感から、ジャーナリストがティーンエイジャー3人の事例を徹底検証した本書をじっくり読んだ。いじめっ子には5タイプいること、私たちがメディアを通して知るいじめ報道は歪曲されていることなどが印象深かった。子どもから話される真実は、その数だけある。 2024/08/05
zushhy
4
いじめは単純ではない。弱い相手を「いじめる」行為で、地位があがる、という陰の報酬があることを、本書で理解した。しかし、完全に断っても子どもは成長できない、と筆者は主張する。大人の世界にはさらに過激な競争があるからね。後半はフェイスブックをはじめとするSNSに直接取材をして、(ぜんぜんアテにならない)対策ぶりを現場で直にみる。(親は、ザッカーバーグを信じてはいけない)。学校に対して要求しすぎる親にも、親にできる以上のことは学校にも無理である、と書く。良書。2014/11/09