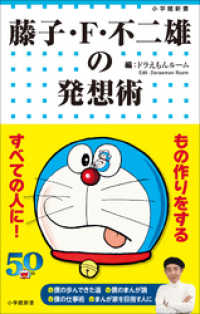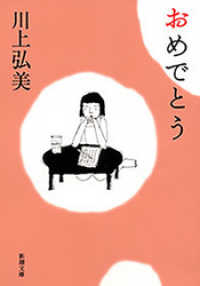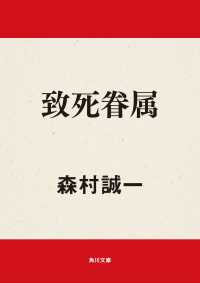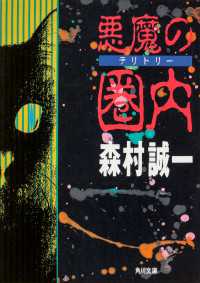内容説明
江戸時代は庶民も楽しんだグルメ社会だった。
和食が世界遺産に登録され、世界中が注目する日本の優れた食文化。四季折々の食材を活かし、繊細な美意識を体現する日本の食文化を見直そうという動きが強まっています。
一日三食の生活スタイルをはじめ、現代日本人の食文化の基本は、江戸時代に形づくられたものです。また、江戸時代は一般庶民までが「グルメ」に目覚めた、世界でもっとも進んだ大衆文化社会でした。
本書では、寿司や天麩羅・蕎麦・鰻の蒲焼といった江戸時代に誕生した料理の詳細だけでなく、高級料亭から居酒屋・定食屋・屋台まで幅広く発達した外食文化、調味料の発達とその影響などについて紹介。さらには、肥料やハウス栽培の発明などこれらを支えた生産技術の革新、都市住民の食欲を支えた流通事情と特産物の開発、レシピ本やグルメガイドの流行、年中行事や儀礼と食との関係、江戸の食育や食養生といった文化的側面など、食を取り巻く環境全体について多角的に考察します。巻末では現在も営業を続ける食の老舗や名店なども紹介しています。
江戸文化歴史検定の受検にも役立つ、江戸の食文化の総合資料です。【ご注意】※この作品には図表が含まれており、お使いの端末によっては読みづらい場合がございます。タブレット端末、PCで閲覧することを推奨します。
※この作品はカラー画像が含まれております。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
天の川
32
思っていたより、うんと濃い内容でした。『天に星、地に花』を読んだ後だったので、江戸や大坂の豊かな食が、百姓達の地を這うような働きの上に成り立つものだと切なくもなりましたが…。江戸時代は出版物も豊富な時代。統計資料・文献資料・浮世絵による視覚資料、全てにおいて充実していることを再認識。カラーページ、図版が多いので、とっつきやすい印象ですが、ちょっとした雑学本とは一線を画す内容だと感じました。2015/03/22
シュラフ
19
江戸時代の食と生活が、江戸の街づくりに大きく関わっていたということが分かる。江東区をまっすぐ東西に流れる小名木川がある。家康が1590年に江戸に入り、真っ先にやったのがこの小名木川の掘削工事。当時 戦略物資であった塩の確保のため、江戸と塩の産地の行徳を運び入れるルートをつくった。後に幕府が安定すると瀬戸内産の下り物に依存するようになる。そのため行徳では苦汁が少なく目減りの少ない古積塩の生産をはじめたという。今も残る小名木川・・・江戸の街の塩を確保する動脈であったと思うとまた別の景色のように思えてくる。2014/10/13
ようはん
18
江戸時代の食文化の本を読むのはやっぱり面白い。こうまで食文化が多彩に成長した時代は諸外国含め無いであろうと思う2025/01/22
るう
8
随分昔の時代と思っていたけど食文化の観点からしたら今食べている食事のほとんどが江戸時代から変わらない。日本中から食べ物が集まり食べ物屋が多くあって色々な番付があったりと華やかな江戸の様子が分かる。文献となる絵も沢山載っていて時代小説好きなら手元に置いておくのも良さそう。また江戸東京博物館に行こうかな。2015/05/24
nizimasu
4
今の和食のルーツは結構、江戸時代に求めることができるのねと確認しつつ読み進める。さすがにこの時代は出版も盛んだったので、様々な資料が残っていて、江戸の鰻屋さんや食肉、天ぷら、それに二八ソバなんて記述もあって、実は、外食のスタイルもこの時代にあったのかとなんとも微笑ましい。江戸の時代も庶民にとっては停滞の時代だった訳で、その中で食を楽しむ。あるいは、海運の発達で、西から様々なものが届くようになったり食の多様性も、今のご当地ブームとも重なる。今も大いなる停滞の時代と食を通じて気づきは多いなあと思わされました2014/08/03