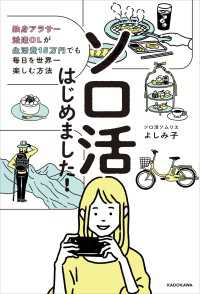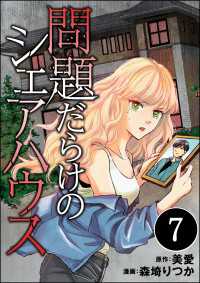- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
芸能の時代といわれる中世は、巫女・傀儡女・白拍子女など、社会の底辺に生きながら人々に救いと娯楽を与えた女性芸能者たちが活躍していた。史料、説話、能などを手がかりに、女性芸能者の実態を描き出す。
目次
第1章 巫女―神への舞
第2章 傀儡女
第3章 遊女
第4章 白拍子女
第5章 曲舞女
第6章 瞽女と女芸人たち
終わりにかえて―出雲の阿国の登場
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Nonberg
10
神代の巫女から、平安の遊芸を彩る傀儡子(くぐつ)、遊女(あそびめ)、白拍子(しらびょうし)、猿楽へ続く室町期の曲舞女(くせまいめ)など、歌舞が男主導に移る近世の前までの女芸能者に文芸と史的文献から光をあてます。古体の歌謡がどう受け継がれてきたのか。筆者自ら能を舞うため「吉野静」「斑女」「山姥」などの演目に残る影響も語られます。芸で身を立てる --『更級日記』に描かれた夜の足柄山中でみごとな歌を披露する三人の遊女をはじめ、祇王や仏御前、静御前などの姿からは、妖艶かつ芸の奥深さに根差す力強さが伝わってきます。2020/11/21
みかん。
2
更級日記の足柄山の遊女は傀儡子女なのかもしれない。緋袴は宮廷に所用があるかつての女性のおそらく公的な正装の一つなのかも。緋袴が比較的におそらくシンプルな構造の衣装なのは臨時に用いることを想定している可能性もあるかと。過去の古い文化が延々と残っている日本は本当に凄いですよ。2025/09/24
芙由
2
古事記のアメノウズメ、三輪山伝説、白拍子の静御前くらいしか予備知識がない状態で読んだが、更級日記とか山家集とか薄れてていた断片的な知識もつながっていってなかなかおもしろかった。能やら神楽やらまったく詳しくないが、古典文学の延長で楽しめるか。2021/02/14
shou
2
古事記などの神事に始まり、主に中世に存在した女性芸能者たちについて。後白河法皇と今様、義経と静御前などの例を文献に観て、彼女達の地位や実態を考察。世阿弥らに影響を残し、やがて江戸の封建制度のなかに消えていく彼女達の存在を共感を持って見送る。2015/02/08
コノヒト
1
芸能とはそもそも何なのだろうか。聴衆観衆の心を揺り動かす技のことだろうか。傀儡子、遊女、白拍子、という言葉を宮武外骨に教わった私なんぞは、それらを売笑婦の異名として認識してきた。芸を売る。淫を売る。いずれにしても客は男だ。そして巫女は神さまの感動を得るために舞う。夕方のテレビのニュースなんかで地域に根ざした神事祭礼を紹介することがままあるけれど、これからは見る目が変わりそうだ。けれども昨今の巫女はアルバイトだったりもするのだ。2016/03/30