- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(健康/ダイエット)
内容説明
子育て本のベストセラーを連発する「受験のプロ」が、勉強嫌いの子どもが確実に勉強好きになる方法を公開! 「なぜ勉強しなければならないの?」とお子さんに聞かれたら、あなたは親としてどう答えますか? そして、勉強嫌いなお子さんを、いかに勉強させるようにしますか?そんな多くの親が抱えている悩みに対し、「教育環境設定コンサルタント」として活躍する著者が、「勉強する目的」を解説し、「子どもが進んで机に向かう環境設定」を公開します。……みなさん、今、お子さんに勉強させ「判断力」と「創造力」を身につけさせなければ、将来「ダマされる」人になってしまいます! でも、本書で書かれていることを実践すれば大丈夫。 「子どもがぜんぜん勉強しない」悩みは、本書で解決できます。【今、なぜ、勉強するのか?の一例】 ●小学生の今が、賢くなれるチャンスのため●「ダマされない」人になるため●グローバル化社会で生き残るため●自分の好きな仕事に就くため……etc.【子どもが勉強好きになるメソッドの一例】●「集中・繰り返し・片づけ」を習慣化●音読とパズルを一緒に楽しむ●家の手伝いは子どもを賢くする●親が本を読んでいる姿を見せなさい●親子で守りたい「テレビのルール」●ゲーム機を取り上げられないならどうする?●外で遊びたい子どもの欲求を無視してはダメ! ●「自問自答」の習慣が健全な心を育てる……etc.
目次
第1章 まず、親が知るべき「今、なぜ、子どもに勉強させるのか?」(偉人たちが伝える「勉強」ってどんなこと? もともとは「勉強」ではなく「学問」だった ほか)
第2章 子どもが生きる未来社会で必要な「賢い」知恵(「ダマす」人と「ダマされる」人 ダマされないためには、まず何をするか? ほか)
第3章 勉強嫌いな子どもに勉強させる「私のやり方」(子どもが夢中になっているときが「賢くなる」チャンス! 「アタマがいい状態」を継続させる! ほか)
第4章 子どもを賢くするために母親が「今」実践すべきこと(家のどこで勉強するか? 片づけの習慣が、なぜ大切なのか? ほか)
第5章 子どもが小学生のときにやっておくべきこと(小学校卒業までに身につけておきたい能力 正確な音読で身につける「国語力」 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bakky
re;
Sayaka
Ken Terada
Hikari Sakai
-
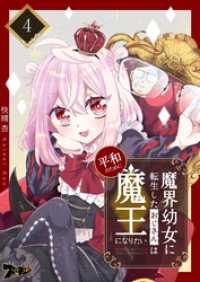
- 電子書籍
- 魔界幼女に転生したおじさんは平和のため…
-
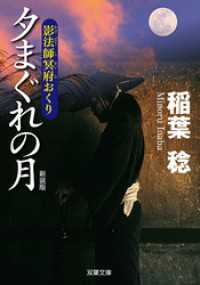
- 電子書籍
- 新装版 影法師冥府おくり : 2 夕ま…
-
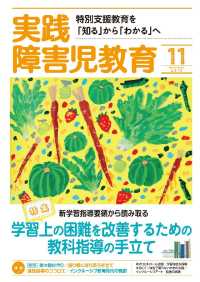
- 電子書籍
- 実践障害児教育2019年11月号
-

- 電子書籍
- オメガトライブキングダム(11) ビッ…
-
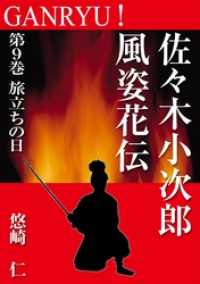
- 電子書籍
- GANRYU!~佐々木小次郎風姿花伝~…




