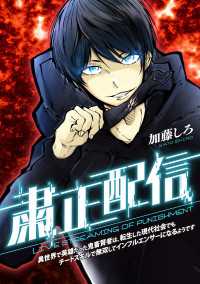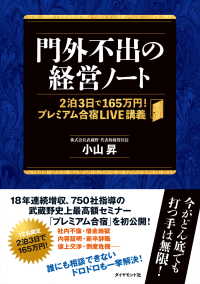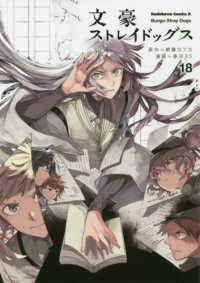- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
室町以前の「文学」を再構築し、身体芸の総合芸術へと変革した能。その代表的な作品の舞台から、能という装置と身体によって顕わになるものを凝視し、逸脱のテキスト論を展開。能の見方を挑発する現代能楽解体新書。
目次
井筒―象徴と幻像
融―スキャンダルの向こう
清経―歴史のなかの女の声
朝長―「花鳥風月」のかなたに
姨捨―老女物というジャンル
鵺―歓待の精神
松風―二人で狂う
大原御幸―歴史への反ドラマ
定家―突き抜けるゴシック・ロマン
砧―夢幻能からの逸脱
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kazuo
5
能の作品論(「井筒」等)。私は「能」の身体性、武道やコレオグラフィーとの共通性からの興味により本書を読んだ。期待していた内容には触れられていなかったが、なぜ「歌舞伎」が庶民の芸能であり「能」が武士の芸能であるのかが、自分なりに少し理解できた気がする。能では、歌舞伎にはない過剰な精神性があり、分かりやすい「勧善懲悪」的な結論は出ない。TVでも地上波とは言わないがBSで(オペラと同程度には)能を放送してもらいたい。ある程度の量を経験しなければ、本質を直接提示するタイプの芸術は理解できるようにならないのだから。2016/03/19
mustache
1
井筒から砧まで、十曲を取り上げた作品論。世阿弥と元雅の作風の違いなど大胆かつ斬新。とりわけ「能はおそらく退屈な芸術である」と断言するのに瞠目した。「退屈な時間のなかで・・・永遠にも思えるほどの記憶が生まれるのも能である・・・退屈など恐れることはない。そこに永遠があるなら、待つしかないのだ。」すごい!2017/01/13
Mitsuaki Shimode
0
宝生閑の話が多く、能評がブレ気味。2015/07/05