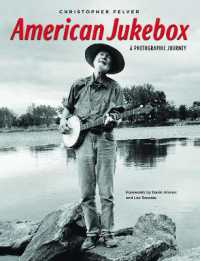- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「ゼロ金利政策」「金融緩和」「アベノミクス」…….この間,金融政策が政治の重要課題となり,日々の暮らしにも大きく影響を与えるようになった.その金融政策はどのように決まっていくのか.日銀をはじめとする世界の中央銀行はどのようにかかわっているのか.金融関連の専門用語も丁寧に解説.今後を考えるための必読書.
目次
目 次
はじめに
第1章 金融政策を理解するために
1 金融政策
金融とは何か/通貨とは何か/中央銀行と銀行券/日本銀行券について/ 「信認」の重要性/現金通貨と預金通貨/資金決済のメカニズム/システミック・リスクへの対応/流動性とは何か/金融政策とは何か
2 金融政策が働く場
資金の流れと金融機関/金融商品と金融市場/金利とは/利回りとは
3 金融政策の決定と実行
誰が決定するか/どのように実行されるか/金融調節はどのように行われるのか
4 金融政策の波及過程
ケインジアン・アプローチ(金利経由)
コラム〓フィリップス曲線
期待の役割/マネタリスト・アプローチ(通貨量経由)/金利との関係
第2章 金融政策の軌跡
1 伝統的金融政策
インフレと国際収支の天井/護送船団方式/金利規制/日銀の政策/金融自由化の時代
コラム〓プラザ合意とルーブル合意
2 金融危機と金融政策
平成バブル/ゼロ金利政策と量的緩和
3 デフレ対応策としての金融政策
「失われた」一〇年?/デフレとは何か/デフレの問題点/インフレの問題点/価格と物価/物価指数について/GDPデフレーターとは
コラム〓GDPデフレーターと交易条件
4 非伝統的金融政策
伝統的金融政策と非伝統的金融政策/非伝統的金融政策/金融政策の透明性/期待への働きかけ/コミュニケーション戦略の問題点
コラム〓複数均衡論
第3章 金融政策と財政・為替政策
1 財政政策との関わりあい
国債について/国債と日本銀行/国債の発行と基礎的収支/国債の負担について/財政節度維持の重要性
2 為替政策との関わりあい
為替相場について/購買力平価説とは/金利平価説とは/金融政策と為替相場との関係/デフレ対応の金融・為替政策/為替市場への介入/介入の不胎化について/円高は問題か
コラム〓マンデル〓フレミング・モデル
第4章 中央銀行が直面している諸問題
1 中央銀行の独立性
中央銀行の独立性とは何か/日銀の法的性格/政府と日銀の関係
2 インフレターゲット論
インフレターゲットとは何か/日銀とインフレターゲット/インフレターゲットのメリットとデメリット/ターゲットの設定主体/ターゲット実現過程での諸問題/名目GDPターゲットについて
3 国債増発下の金融政策
白川体制下の金融政策の特色/黒田体制下の量的・質的金融緩和政策/出口問題/準備への付利と準備率の活用
第5章 デフレに対する処方箋
1 デフレ下の金融政策をめぐる議論
翁〓岩田論争と植田裁定/リフレ派と反対派の主張/非伝統的政策の効用と副作用/リフレ派・反対派の論争再論
2 金融政策の波及過程再考
マネタリスト・アプローチの問題点
コラム〓ワルラス法則
準備預金に金利を付けることをめぐる議論
コラム〓準備の性格
量的緩和と信用緩和
3 デフレの真因とそれへの処方箋
本当にデフレだったのか/処方箋を考える
コラム〓人口動態と経済成長
三本目の矢の重要性
おわりに
主要参考文献
主要中央銀行の金融政策措置一覧
索 引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
KAZOO
海二見
たこ焼き
こばやしこばやし
-
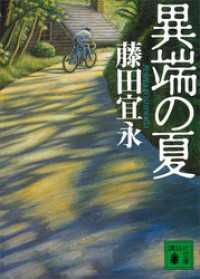
- 電子書籍
- 異端の夏 講談社文庫
-

- 電子書籍
- 足立華 最強の【競泳水着】【Gカップ】…