内容説明
コメンテーターでなくても、なにかとコメントする機会が増えている時代です。ビジネスマンにしても、会議や飲み会での会話ばかりか、メールの返信に意見をプラスしたり、フェイスブックで「いいね!」にひと言添えたり、ツイッターでニュースに自分なりのコメントをつけたり、LINEの投稿を気の利いたものにしたり……。“ああ、面倒くさいったらありゃしない”と思っている人も多いのでは? そこで、複眼で物事を考える姿勢をもったうえで、コメントの内容をどう組み立てていくか。「情報は整理しない」「情報はタテ軸とヨコ軸に置いてみる」「すべてはグレーと考える」「情報はストーリーで発信する」「他人と同じことは絶対に言わない」「刺さるコメントよりも、しみ込むコメントを」「ボケる力を磨く」等々、『ニューズウィーク日本版』元編集長がマル秘ノウハウを初公開。“情報がありすぎる社会”を生き抜く必須スキル、「情報力」と「コメント力」が磨ける1冊です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
あちゃくん
116
竹田さんの訃報を聞き、積読してあったものを引っ張りだして、追悼の意味を込めて読み終えました。この本の中でエピソードとしてあった、「勝者のキス」へのコメントなど、竹田さんの知性が随所に感じられ、本当に憧れる知性の持ち主だなと思いました。竹田さんのラジオやテレビでのコメントを今後聞けないと思うとホント残念です。ご冥福をお祈りします。2016/01/16
かまど
35
「情報との向き合い方を知る」 ニューズウィーク日本版の元編集である著者が、情報過多社会での情報との付き合い方を指南してくれる一冊です。 SNS、キュレーションアプリ、Webサイト、テレビ・ラジオ。 世の中には情報を発信する媒体が多くあり、人は一日中、情報のシャワーを浴びている状態です。 しかし、いくら情報が多いとはいえ、その情報をコントロールするのは自分自身にほかなりません。 (つづく)2016/04/04
白義
21
「よくわからないことにはコメントするな」「鋭いことを言おうとして物事を単純化するな」とコメンテーターの身でありながら発言出来る時点で、著者のテレビでの活動を知らなくても十分興味を引かせるのに成功している。内容は情報過多な社会でいかに自分自身が情報をコントロールしていくのか、というのをジャーナリスト、編集者の立場から語った情報整理術。多角的、複眼的に物事を見ることとスピードをいかに両立するかという点で特色があり、ツイッターなどで迂闊な発言をしない注意深さも身に付きそう。きっちりしてなくて緩い分使いやすそう2015/11/26
佐藤一臣
19
竹田圭吾さんの告別式の弔辞で、津田大介さんが「日本一のエアコン」と話していましたが、竹田氏のコメントは本当にそれを体現していたし、それが出来た理由が、この書籍に余すところなく書いてありました。情報を自分はどうやって取得し、どう編集してコメントに生かしたのかがよーくわかりました。SNSをやっている素人の個人がコメントする際に活用することが間違いなく出来るでしょう。でも、ツイッターの評価がやけに高い意見はあんまり賛同できませんでした。2016/01/18
福蔵
13
「今、自分にはコメント力が足りないかも」と感じて手に取った本。0から情報を生み出すことは厳しいが、自分ならでは情報の取捨選択ができて、情報発信する「型」のようなものを意識すればコメントする力はついていくのかも。2015/01/19
-

- 電子書籍
- 犯罪捜査の心理学: プロファイリングで…
-

- 電子書籍
- 白馬に乗れない王子〈カッファレッリ家の…
-

- 電子書籍
- 大富豪と置き去りの花嫁【分冊】 11巻…
-
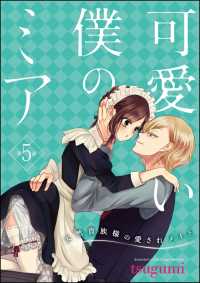
- 電子書籍
- 可愛い僕のミア 天然貴族様の愛されメイ…
-
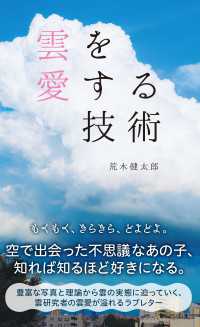
- 電子書籍
- 雲を愛する技術 光文社新書




