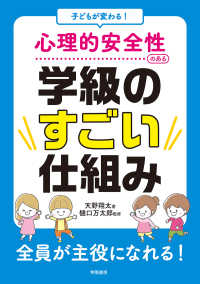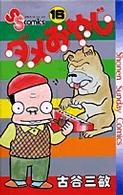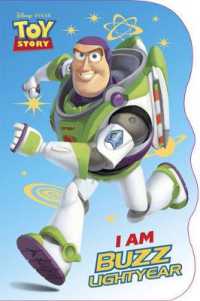内容説明
高齢者の増加と高額医療の出現によって”医療の過剰消費”が行われている日本。”国民皆保険”崩壊の可能性が近づく中で、医療はどのように変わるべきか? 病や老いとの付き合い方を考えるために必携の一冊。
目次
序章 あなたの「命の値段」はいくらなのか?
第1章 高額化する医療
第2章 壊れる国民皆保険
第3章 医療政策を変える経済学
第4章 日本と対極の国・スウェーデン
第5章 私たちはどのように長生きすればよいのか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
29
世界では、アンダーグラウンドで臓器売買が日常的に行われている。残念ながら他人事ではない。日本人が〝買い手〟として、貧しい途上国から臓器を買うケースもある。貧しい国では、死体から臓器を取り出して売り払う臓器ビジネスが病院ぐるみで行われるところもあり、臓器売買目的の殺人事件、誘拐事件さえ頻繁に起きている。日本人が臓器売買というシステムの中に、優良な買い手として組み込まれる最大の理由は、多くの国で認められている脳死による臓器提供が制限されていたためである。 家族の理解は必要だが、原因が本当なら見直すべきだろう。2019/11/28
うさうさ
19
サブタイトルの「国民皆保険」の弊害、崩壊が中心で、外国との医療の受け方、考え方の違いについて書かれている。 保険で医療が安く、早く受けられるようになってまだたったの60年という事に驚く。安く受けられる事で医療の過剰消費が起こり国の医療費を圧迫。救急車をタクシー代わりに使うとか、高齢者がサロンのように医者通いとかは論外だと思うけど、もし医療が自費なら風邪で医者にはかかれないな。 医療技術の進歩で死ぬ病気ではなくなったが慢性疾患になり、これも医療費を圧迫。 色々難しすぎてわからんね。。。2018/11/29
1.3manen
11
秘密会議のTPP。医療も例外でない。21分野に医療、公的医療保険制度は無いが、物品市場アクセス、知的財産で医療は関係する(28頁)。保険は助け合いの制度(71頁)。「花見酒経済」とは、身内で売買を繰り返すことで、見かけ上では売り上げが伸びたように見えるが、実質は変わらない事象(88頁)。経済学は社会科学の女王(92頁)。肥満者は危機回避傾向が低い(107頁)。そうだと自覚する。年金も保険料だけ取られて自分が受給する段になるともらえないように、これから先は金持ち患者でないと医療機関も相手にしないなら不安だ。2013/10/07
ほよじー
10
★★★高齢者の場合、健康と病気の中間に虚弱という状態がある。虚弱は一人で日常生活を送ることが難しい状況。虚弱にならないことで施設に入所することなく生活が可能になる。では何に気をつければいいのか?やはり予防である。禁煙、健康的な食事、適度な運動に尽きる。とくに動くことは虚弱予防になり、PPK(ピンピンコロリ)を達成するカギになる。逆に、軽い脳梗塞で入院し、廃用症候群で入院が延長し、誤嚥性肺炎で寝たきりになり、人工呼吸器をつけ、心臓・腎臓が悪化して死亡、、という経過は本人も家族も医療費も大変なことに。2018/07/03
ERNESTO
4
イギリスでは、1年間で質調整生存年(生活の質を加味した寿命)あたりにかかる費用が、£3万(約¥460万)以上の場合には保険治療の推薦を得られにくく、£2万未満なら保険支払いの推薦になる。 体調が悪い1年と健康な1年の価値を数字で表しており、当然高齢者の質調整生存年は高くなる。 このような合理的経済学で、イギリスでは命の値段が決められており、日本の厚労省の審議会である中央社会保険医療協議会でも、この議論が少しずつ行われている。 2013/10/18
-

- 和書
- 弁論集 西洋古典叢書