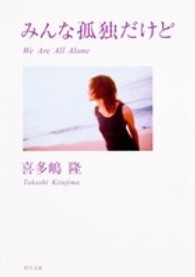内容説明
ヒトの大きな脳が作り上げた「社会」は、私達の生きる基盤でもあり、悩みのタネでもある。この社会という厄介な問題を脳はどう処理しているのか。その謎を解く鍵は「社会脳」にある。なぜ他人の視線が気になるのか。赤ちゃんは生きる術をいかにして身につけるのか。ネットで誤解が生じやすい理由とは――ロンドン在住の若き科学者が、自らの軌跡と共に「社会脳」研究の最前線を平易に説く。知的興奮に満ちた一冊。
目次
ダーウィンの遺産
生物学から人間に迫る
社会脳とは何か
他人の心を読むということ
自閉症児が教えてくれる
視線の先にあるもの
“見られている感”のメカニズム
子どもは育つ、脳は変わる
赤ちゃんは知っている
赤ちゃんの脳、社会に挑む
“目が合うこと”のメカニズムと発達
思わずやってしまうこと、言われればできること
脳が動かす社会、社会が育てる脳
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ほよじー
17
★★★相手の視線、表情、仕草、声の抑揚などの情報を素早く読み取り、自発的に反応する社会脳。社会脳は無意識のうちに他者とのコミュニケーションに大きな役割を果たしている。ネットでトラブルが起きやすいのは相手の顔が見えないため。社会脳をテーマに奮闘する一人の若手研究者の、過去から現在に至る研究の経緯(高校〜大学〜修士〜博士)が分かる。理系の学生にオススメ。2013/12/10
スパイク
16
おもしろ~い!わかりやす~い!脳が社会的な問題をどのように処理しているのかを自閉症児・者との比較で解き明かそうという内容。内容も面白いが、本の構成がイイ。著者が何故このテーマを選んだのか、そしてどのように対応してきたのかが時系列に沿って描かれていて、著者の成長の過程まで楽しむことができた。すんばらしい論理や発見は見当たらなかったが、こういう好奇心と、地道な努力の積み重ねが、大きな成果になるのでしょうね。私も巨人の肩に乗せてもらっていろんなものを見させてもらって楽しませていただきました。2014/08/03
calaf
13
自閉症児の社会脳は、能力には全く問題ないものの、自発性(日常生活の中で能力を発揮するべき時を逃さず使いこなす事)に問題がある状態らしい...以前別の本で読んだ事がありますが、それにしても、赤ちゃんを使った実験は大変だ...2013/11/01
東雲
13
コミュニケーションにおいて”視線”の果たす役割を研究した本。 人間の脳はなぜこんなに大きいのか。それは大きな群れ=社会で生きることに関係している。という脳科学の仮説から始まり、自身の科学との出会い、なぜ現在のような仕事に就いたのか?脳科学の入門書のようになっている。普段こういった専門性の高い本を読まないので勉強になった。赤ん坊の視線への共感は生後間もないうちにすでにあるのね。驚いた。また自閉症児との比較もていねいに書かれていてわかりやすかった。大脳新皮質というのは大人になっても成長するのか。2013/09/13
小鈴
10
これは面白かった。顔や他人の動きなど社会的な問題を説く脳の働きを社会脳(social brain)と呼び、ブラザーズが1990年に発表した論文から始まった。著者は主に視線の研究(ほかにあくびの研究!)を自閉症児を対象に行い、人にとって見るということはどういうことなのか解き明かしていきます。また、研究者になるために大学時代から修士、博士、ポスドク時代の問題関心の設定から研究を深めていく手続きやきっかけ、理論を作る過程までオープンにしている。日本の研究者で理論づくりについて書いているものは少ないのでは。2013/09/09
-

- 洋書
- Jassy Bear