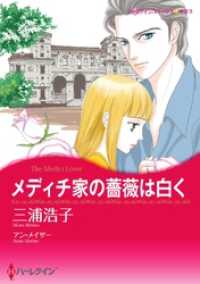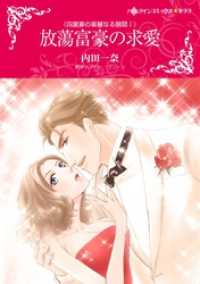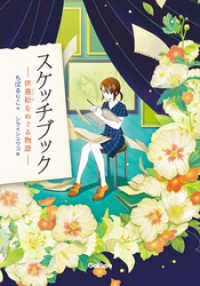- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
徳川譜代の大名・井伊家に仕える大場家は、代々世田谷の地で代官職を務める家柄だ。代官として、井伊家の無理難題には応えなければならないし、それに対し領民からは突き上げられるし、その姿は、まるで現代の中間管理職である。井伊家の財政破たんの危機に際しては、世田谷の領民が供出金を出しあって支えたり、銃が足りないといえば、世田谷領民が最新式の銃を井伊家に寄付したり。まさに、世田谷領なくしては成り立たないほど、井伊家の江戸での生活を支えていた。そのまとめ役が、代官である大場家。幕末といえば、京都での志士たちの活躍が取り上げられることが多いが、江戸でも時代の荒波に翻弄されながら、毎日を必死に生きる人々がいたのだ。歴史上、無名の人々の視点から見た、もう一つの幕末維新史である。
目次
序章 桜田門外の変の衝撃―維新のはじまり
第1章 大場家と世田谷領―いくつもの顔を持つ代官
第2章 江戸の混乱に巻き込まれる―開戦危機
第3章 大場家御家断絶の危機―鉄砲を持った農民たち
第4章 関東の騒乱と世田谷―幕府の消滅
第5章 明治維新と大場家―消えいく江戸
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
AICHAN
42
図書館本。幕末から維新にかけては時代が沸騰して大きく動いた。多くの英雄が出た。彼らのことはよく知られている。歴史の表面に現れなかった庶民は、この動乱をどう見ていたのか。当時の世田谷代官夫婦、特に妻の日記によると、ペリーの来航、桜田門外の変、戊辰戦争等々の動乱により、混乱と困惑が続いたことがわかる。武家は農民の人足なしでは戦もできないため、度重なる御用人足の徴発、井伊家による農民兵の整備要請による鉄砲稽古の開始等々で農民たちは激務だったのだ。年貢や上納金を取るだけでなく、武家というのはまったく勝手だ。2018/11/04
ようはん
25
時代劇で描かれるような悪代官は実際には存在しないという話ではあるが、この本を読んでみると代官という立場は上と領民の板挟みになる苦労人ポジションであるのが分かる。まだ農村地帯だった世田谷を統治していたのは彦根藩井伊家で本書の主人公である大場氏が世田谷代官として飛び地の統治を代々行っているが、大身の井伊家故に江戸屋敷からの命令で物資や人員の調達を度々行わなければならならなかった。多大な領民の負担を和らげる為に尽力し、一揆や軍事調練など幕末の混乱にも立ち向かっていく姿には同情する。2025/01/04
ホークス
21
井伊家代官として、世田谷方面二十ヵ村(約二千石、住民約五千人)を治めた大場家。本書は当主と妻の日記を頼りに、幕末の実像に迫っていく。冒頭、桜田門外で主君井伊直弼が急死。井伊家の御用に苦慮してきた大場家と領民は、今度は加速度的な時代の変化に見舞われる。和宮輿入れや対英戦への労役や金品負担。内戦による治安悪化。農民の軍事訓練開始。その渦中39才の当主大場与一は病没し、国中が内戦化する中、3年後には幕府も消滅する。夫の死後も日記を書き続けた大場美佐は、人柄まで感じられ、刻々と変わる状況を一緒に追っている様だった2016/10/10
maito/まいと
20
世田谷が井伊家の飛び地、飛び地が江戸の食料・軍事基地、などなど知らなかったことが次々と飛び出す1冊。つくづく、記録って大切だ、本人からすればただただ毎日のことを記録しただけ(大場男性陣は役目だったけれど)。でもこの記録が、井伊直弼暗殺から明治までの混乱した世情を映し、跡取り不在の大場家の駆け引きを後世に残し、そして地道なお役目の積み重ねが、混迷の世の中を生き残る大きな要素になることを、教えてくれた。淡々と進む文章ながらも、学ぶべき事がたくさんある1冊だ。2018/09/16
まー
13
彦根藩代官大場氏の妻の日誌から見た幕末の江戸は庶民目線で維新を語っていて当時の彦根藩下屋敷である世田谷界隈の空気感や時代の変化を身近に感じました 以外なのはあの辺り松陰神社の有るあたりは長州藩下屋敷も有ったのですよね2024/08/11