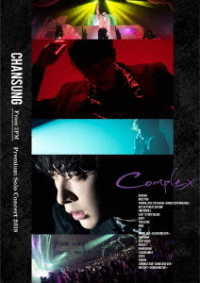- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
経済はむずかしい。簡単に理解できる本はないだろうか。
こんなことが言われるのは、日本だけではないのですね。アメリカでもしばしば聞かれる声だそうです。では、それに応えよう。こうして生まれたのが、この本です。
この本は、『スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 ミクロ編』に続くものです。原著は1冊にまとまっていますが、日本語版は、読者の便宜を考え、2冊に分けました。
まずはミクロ編を読んだうえでマクロ編に進んでほしい。著者は、そう考えて、この順番にしています。
マクロ経済学の「マクロ」とは巨視的な見方のこと。単にミクロ経済学を大きくしたものではなく、経済全体を大づかみにする学問です。
個々の企業や人びとの経済活動を分析するのがミクロ経済学ですが、そうした個々の活動の集大成の結果、一国の経済や世界経済は、思わぬ動きをすることがあります。
それを分析するのがマクロ経済学です。
著者のティモシー・テイラー氏は、経済学者。アメリカ経済学会発行の雑誌の編集に長年携わってきました。全米各地の大学で経済学の講義も担当し、スタンフォード大学とミネソタ大学では「学生が選ぶ講義が上手な教師」の1位を獲得しています。
アメリカの有名大学といえば、東はハーバード、西はスタンフォードです。極めて優秀な学生たちが熱狂したテイラー先生の講義とは、どんなものだったのか。この本で体験してみましょう。その教え方のうまさは、実際に本文を読んでいただければ明らかです。
経済の基本を、身近な具体例を引きながら、鮮やかに説いていきます。
目次
マクロ経済とGDP―経済全体を見わたす目
経済成長―生活水準を上げるたった1つの方法
失業率―なぜ失業者が増えると困るのか
インフレ―物価高が給料を食いつぶす
国際収支―アメリカは世界に借金を返せるのか
総需要と総供給―需要が先か、供給が先か
インフレ率と失業率―マクロ経済の巨大なトレードオフ
財政政策と財政赤字―国の財布の中身をのぞき見る
景気対策―需要がないなら穴を掘らせろ
財政赤字と貯蓄率―赤字のツケを払うのは誰か
お金と銀行―貸せば貸すほどお金は増える
中央銀行と金融政策―誰が世界の経済を動かすのか
金融政策の実践―武器の使いどころを考える
自由貿易―なぜ外国からものを買うのか
保護貿易―貿易をやめると幸せになれる?
為替相場―通貨高で得をする人、損をする人
国際金融危機―投資ブームと為替の恐怖
世界経済をどう見るか―未来を切りひらく視点
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ito
ちゅんさん
PONSKE
三井剛一
三井剛一
-

- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 06年5月27日号 …