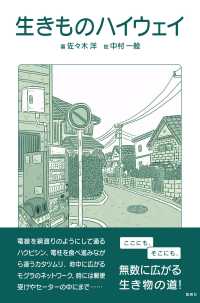- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「好き嫌いはいけない」「大人の言うことはきちんと聞きなさい」「基礎が大切」「わがままはダメ」「嘘はつかない」「秘密は持たない」・・・・・・。しつけや教育の現場でよく聞かれるこの言葉。でもそれって本当の事だろうか?注目の精神科医が最近のクライアントの傾向から現代のしつけ、教育の常識に強烈にダメ出しする。人間らしい真の思考を目指すためのヒント。(講談社現代新書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
53
確かに教わるだけでは限界があることはよくわかった。しかし著者の経歴がすごくて驚く。2013/03/10
ほよじー
16
★★★★★教育には弊害がある。好奇心に基づき自発的に行われるものは教育ではなく学習。学習には自ずと知的探究の喜びがある。教育は機械的、受動的作業。善/悪の二者択一(サル的な考え方)ではなく、「頭」と「心=身体」の二次元で考える。日本の学校は個人の育成よりも、集団生活のスキルを身につけさせる場。学生服、体操服、持ち物制限、時間割、朝礼での整列。まずは集団ありき。これはムラ的共同体の考え方に由来する。ムラ的共同体では個人や個性は認めない。いかに良きムラ人になるかを叩き込まれるだけ。2017/06/12
ヒュンフ
10
「普通がいいという病」のツァラトゥストラの解釈や精神の変容を知り、その次作という事で手に取った。作中のオオカミ的な心と意味(納得)を自分はエンジンと捉え、サル的な算術をツールとして捉えた。チャック・パラニョークのファイトクラブに近い。自発性と能動性こそが行動のキモであり、それを制御する親や管理は打倒する存在。自分は片親は悪いことと思っていない、母親が欠ければ料理を覚え、父親が欠ければ稼ぐ事を覚えるからだ。それよりも仲のいい何でも話す友達親子こそまずい。あくまで個人なんだから秘密は必要。その先に自立がある。2020/12/11
ももたろう
10
読友さんの感想に刺激されて手に取った。本書では、マニュアル人間、指示待ち人間を量産する現代の教育の問題点を浮き彫りにしている。教育によって「思考停止人間」が増えているのは、その通りだと思う。自分もその一人だし。ちょうど昨日読んだ岡本太郎は、「良い子」とは正反対の「問題児」だが、彼のような反抗精神旺盛で常識を疑い、己の感性を磨き続けるような人間が、何事かを為すのだと改めて感じた。また、「守破離」の考え方が大事だと思った。「守」の段階は、愚直に師の学びを吸収すべきとある。ここを履き違えてはならないと感じた。2015/11/30
たく
10
大学生の私には、守破離の学ぶ姿勢を意識することの重要性が心に響いた。教育に関する様々なアンチテーゼ・ジンテーゼが記されており、親を含めて広い意味での「教育者」は全くこの通りにとは言わないまでも、本書の意見を知るべきだろう。2013/10/15