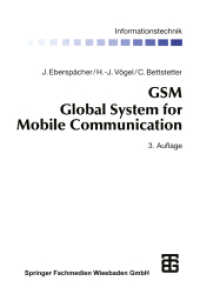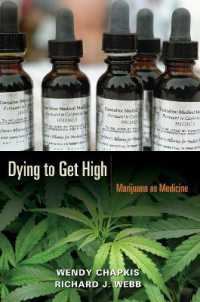- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
「イノベーションを成功させるために何をすべきか」を明らかにするのが本書の狙いです。著者は元ホンダの技術者で、周囲に反対されながら16年間にも及ぶ技術開発を続け、日本初のエアバッグの商品化を実現させました。
ホンダには、イノベーションを成功に導くための企業文化と仕掛けがあり、「ワイガヤ」「三現主義」「ホンダフィロソフィー」などがよく知られていますが、それを単純に解説するだけでは「成功のためにすべきこと」を明らかにできません。本書は、ホンダの開発現場を知り尽くした著者が、こうした企業文化や仕掛けの内容だけにとどまらず、実際の技術開発プロジェクトの最前線で、それらがどう作用し、その結果、いかにしてイノベーションを加速させているかを徹底的に追求することで、ホンダのイノベーションの神髄を明らかにしていきます。
あたかもホンダの技術開発に立ち会うような臨場感。自分の意見をはっきりさせないで上司に頼ると「俺が死ねといったなら、おまえは死ぬのか」と叱咤され、落ち込んだ時には「キミには500億円の価値がある」と持ち上げられる。そして、「ああ、2階に上げられて、はしごを外された」とぼう然とたたずむ技術者がいる。まるで挑戦者たちの息遣いが聞こえてくるようです。
本書は、『日経ものづくり』誌で読者から圧倒的な支持を受けた連載を基にしたもの。一部を日本経済新聞電子版に連載し、こちらでも大人気に。待望の書籍化です。
目次
絶対価値―さあ、未踏の技術に挑もう
イノベーション包囲網―なぜ上司や周囲は反対するのか
本質的な目標―良い目標がイノベーションを導く
哲学と独創性の加速装置―息づく本田宗一郎氏のDNA
ワイガヤ1 高貴な本性―三日三晩話すと何かが起こる
ワイガヤ2 心の座標軸―愛について、何を知っている
三現主義―まずは現場・現物・現実と心得よ
現実的とは―エアバッグで子供を殺すな
異質性と多様性―あなたは「どう思う」、そして「何がしたい」
学歴無用―答えのない問題を解く〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たー
文章で飯を食う
イノベーター
Haruki
人工知能
-

- 電子書籍
- 47都道府県の歴史と地理がわかる事典 …
-
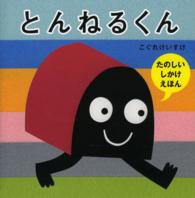
- 和書
- とんねるくん