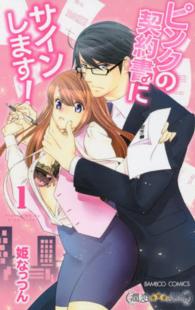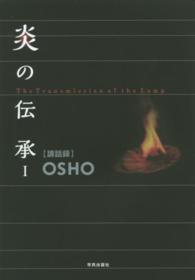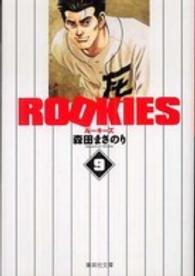- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
218
5章からなる本書には、様々なスタンスの「非アメリカを生きる」アメリカ人たちが描かれている。そして、これを語る著者自身もまた日本生まれではあるものの、今ではアメリカ国籍を持つアウトサイダーの一人である。巻頭を飾るのは、北米最後の野生インディアン(本書での表現)イシの物語。章末にはサプライズも用意されていて、思わず震えが走った。第2章で描かれる、スペイン市民戦争に国際旅団の一員として参加したジャック・白井のボーダーレス人生も興味深い。そして、ジャズから初めて、やがてジャズを超えていくマイルス・デイヴィス。⇒2015/07/02
或るエクレア
11
アメリカに生きる少数派の人の考えが少し分かった気もするが、共感できるかと言われるとほぼ無理な気がする。多くの人が安心や信頼を置くためにはある程度の歴史的継続性や血のような普遍性が必要なのではないか。独立宣言の理念や独自の仏教を広めても多数派と上手くやっていけるとも思わない。少数派から歩み寄る勇気こそ必要なのではないかと思った。2017/02/26
Myrmidon
5
「べ平連」に参加後、「思想の科学」編集代表などを経て、ユダヤ人女性と結婚してアメリカに住んでいる著者のエッセイ風の文章。経歴を見て「ああそういう人ね」と理解できる感じだが、評論というよりコラムか心情吐露みたいなものだろうか。ある世代のあるタイプの人々が今も変わらない様子を見られるのは悪くない。皮肉ではなく。また、「屋根の上のバイオリン引き」など勉強になる話もけっこうあったが、中でもアーシュラ・ル=グインのバックグラウンドが垣間見られたのは収穫。2012/08/08
どんぐり
4
アメリカの1歳未満の出生率が、ヒスパニックや黒人・アジア人などの非白人が50.4%を占め、はじめて白人の49.6%を抜いた。来る将来、アメリカの白人はマイノリティに降りて、国家としてのアメリカは複数民族国家となっていく。日本は単位民族国家にあげられるが、室謙二は80年代にアメリカへ移住し市民権を得て、日本人として例外を生きること、非日本人として、相対的で行動的な思想を生きることをめざしてきた。本書は非アメリカ人として生きてきた人を追って、非アメリカ的アメリカ人について思考を重ねる。ナショナリズムを考える本2012/09/06
yokmin
3
『非アメリカを生きる』とは どうやら『マイノリティーとしてアメリカに生きる』のことのようだ。 元ベ平連活動家、「思想の化学」編集代表で「なにもアメリカ人になる必要もないのに、アメリカ国籍までとってしまった」(P-2)著者のアメリカ論。 アメリカも懐の深い国ではある。2012/10/28