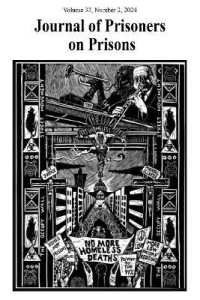内容説明
地球は謎の塊である。その塊からエネルギーを次々に獲得し、万物の長となった人類は、今やエネルギー中毒に罹っている。なぜこんなことになったのか? そもそも地球の定員は何人か? 宇宙から飛来した石油の源、毒ガス開発学者が生み出した新肥料、未来の新エネルギー……第一線の地球科学者が工学、文化人類学、文学などの広範な最新知見を縦横に駆使し、壮大な物語を綴る。科学と文明史が見事に融合した快作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
48
天然の原子炉ってあるんだな。色々なエネルギィの成り立ちとか普及の歴史って意外に知らなかったがよくわかった。2012/07/05
ピンガペンギン
26
人間は生態系のなかで増えすぎている。全肉食動物の取り分が3京キロジュールに対して、今の人口の最低必要量が2京キロジュール。便利なくらしの維持以前に、必要な食料生産に原発150基分のエネルギーが必要だという。リスクをゼロにはできない。バランス感覚が求められるという。第10章に地球のサイクルと生物サイクルの図がある。炭素の輪廻転生から抜け落ちたものが海底に堆積しており、だんだん炭素がサイクルから抜けていくが、炭素は火山活動によって補充されるという。人間が自然の一部なのだと事実として理解できる。2025/04/27
文章で飯を食う
21
地球のエネルギーがサイクルとして回っているので、一部を加速したり減速させると、思いがけないところで、渋滞が生じる。もし、有機農業を実施して化学肥料を全廃すれば、何十億の人が飢えることになるだろう。少なくとも、ほぼ、全国民が農業・漁業などに従事して食料生産以外の事はできなくなるだろう。さらに化石燃料の使用を止めれば、江戸時代に戻る他あるまい。再生可能エネルギーの利用は、まだまだ遠い。原子力に引退を願うには、長い年月とエネルギー、つまり金が必要だ。細い道を誤りなく進む以外、人類に未来は無い。2016/05/22
いっしー
19
東日本大震災後にあらためて考えるエネルギー問題。炭素、窒素から始まり石炭、石油、果ては赤潮まで、意外な話の成り行きに興味を持たずにはいられませんでした。石炭から石油を作る話など、文系でもそれほど気負わずに読める本です。オススメですね。2015/12/08
鐵太郎
14
エネルギーから考える地球の歴史、成り立ち、科学。窒素固定物質、化石燃料の成り立ち、人工燃料、石油とは何か。植物が固定する炭素、徐々に減っていく酸素、原子核エネルギー。しっかりと足が地に付いた理系の人が解説するエネルギーの話、いいね。2016/04/09
-
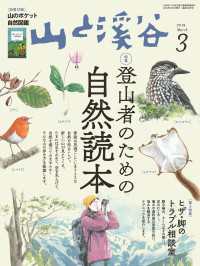
- 電子書籍
- 山と溪谷 2019年 3月号 山と溪谷社
-

- 洋書電子書籍
- オックスフォード版 ホワイトカラー犯罪…