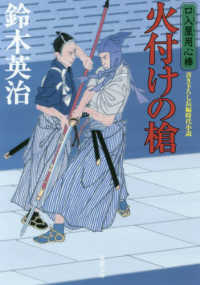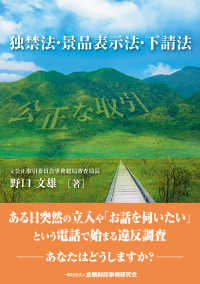内容説明
目の前を悠然と流れる筑後川。だが台地に住む百姓にその恵みは届かず、人力で愚直に汲み続けるしかない。助左衛門は歳月をかけて地形を足で確かめながら、この大河を堰止め、稲田の渇水に苦しむ村に水を分配する大工事を構想した。その案に、類似した事情を抱える四ヵ村の庄屋たちも同心する。彼ら五庄屋の悲願は、久留米藩と周囲の村々に容れられるのか──。新田次郎文学賞受賞作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yoshida
173
九州の久留米藩を流れる筑後川。水利に恵まれない高田村では二人の村人が、筑後川から水を汲み上げ、水口に流す「打桶」を数十年に渡り行ってきた。それでも水は足りず高田村や近隣の村では、農耕に苦しむ。高田村の庄屋である、山下助左衛門は長い年月をかけ筑後川を巡り、ついに堰渠建設の構想を藩に願い出る。山下と志を同じくする庄屋達が集まる。彼らに共通するのは「無私」ということだ。この事業で自分達の身代、更には命も喪っても構わない。これにより、村人の生活が豊かになるのが悲願である。滋味溢れる文体。清々しい感動がある作品。2017/05/17
佐々陽太朗(K.Tsubota)
92
知人の推薦本。帚木蓬生氏の本は初。なんの予備知識も持たずに読み始めたが、すぐに物語に引き込まれた。ここには真心がある。飢えや貧困ゆえの苦しみ、悲しみ、絶望。それでも生きよう、自分の役割を全うしようとする強い心がある。そしてそんな民に人間らしい生活と救いをと立ち上がった五庄屋の姿に心が震えた。上巻だけで何度も涙した。読んでいる間、ずっとアフガニスタンで非業の死をとげた中村哲氏のことが頭にあった。さて下巻を読もう。2021/03/18
naoっぴ
80
筑後川流域にありながら、地形的に水が引けず稲田は常に水不足。作物は満足に育たず飢えと貧しさの苦しい生活を強いられていた村々の、子孫の生き残りをかけた悲願の治水計画は果たして実現できるのか。庄屋たちの、すべてを投げうつ命がけの志の清々しさと強さに圧倒されています!いざ下巻へ。2018/05/02
のぶ
77
まだ上巻を読む限りだが、時代は江戸後期。当時の治水は大変な事業だっただろう。場所は九州、久留米藩の筑後川下流域。大河が近くを流れているのに、稲作に使う水の導水に大変な労力を弄していた。5人の庄屋が堰を築こうと立ち上がる話。上巻では堰建設の具体的な行動はまだ出てこず、農作業の大変さの描写が多い。登場人物の描写がとても丁寧で、当時の苦労が読み手に伝わってくる。これから工事が始まろうかというところで上巻は終わり。この先どうなるのか目が離せない。感想は下巻の後で。2017/12/22
NAO
55
江戸時代、久留米藩の筑後川と巨瀬川の間に広がる水に見放された江南原地区の五庄屋が、身代と自らの命をかけて、筑後川に大堰を設け新しい水路を作ることを許可してほしいと藩に嘆願した。『水神』は、江南原の生葉郡高田村庄屋の下男元助を通して、江南原の窮状、大堰建設嘆願までの経緯、大堰が出来るまで、が描かれていく。ようやく願いが叶えられそうになったというのに、「そんな大事な話なのに、聞いていなかった」と言う、新しいことを始めようとすると必ず起こる横槍を入れたがる政治家たちのような他村の庄屋たちの逆嘆願に怒りを覚える。2021/11/25