- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
近年、発達障害と診断される子どもが急増している。その原因は、子ども自身にあるのではない。少子化など社会変化のなかで、大人の「子どもを見る目」が大きく変化したのである。それは「生きにくくさせられている子どもの増加」でもあった。本書は、発達障害をめぐる様々な混乱を取りのぞくために、最新の科学的知見をもちいて、子どもの発達を胎児期にさかのぼって検証し、発達障害児が〈子ども集団〉のなかで自ら活き活きと育つことの重要性を提案した一冊である。【目次】第一章 発達障害をめぐる混乱――発達障害はなぜ増えたのか/第二章 発達障害とは何か/第三章 発達障害の子どもの運動と知覚――「コミュニケーションの障害」を問い直す/第四章 見る・聞く・感じる世界が違う子どもたち――発達障害の発生プロセスを考える/第五章 障害があっても安心して暮らせる町/第六章 子どもは<子どもの世界>で育つ――「ひとり」を見る、「みんな」を見る/あとがき
目次
第一章 発達障害をめぐる混乱――発達障害はなぜ増えたのか
第二章 発達障害とは何か
第三章 発達障害の子どもの運動と知覚――「コミュニケーションの障害」を問い直す
第四章 見る・聞く・感じる世界が違う子どもたち――発達障害の発生プロセスを考える
第五章 障害があっても安心して暮らせる町
第六章 子どもは<子どもの世界>で育つ――「ひとり」を見る、「みんな」を見る
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さおり
67
その昔、福井で活躍されていたお医者さんの本。残念ながらお会いしたことはないが、お噂はかねがね、という感じだったので、1度著書を読んでみようと思っていたの。大切なことが、とてもわかりやすく書かれている本だった。私も最近やっとそれに気づいたんだよ!みたいなことがいろいろあったが、書かれたんは2011年・・・私、流行遅れな感じ。私が大好きな応用行動分析は、全否定だった。でも、わかるんだ。どっちの主張ももっともなんだよ。もっともっと勉強して、こどもたちの今日と明日を守りたい。2015/06/07
ゆう。
44
僕は医学的なこと、心理学的なことはわかりません。ただ、発達障害を正しく理解していくことが大切だし、今ある社会にただ適応させること(学校などの適応も含め)は違うと感じています。その子がその子らしく生きるために様々な療法はあるのだとも思います。この本は、一つの考え方が示されていましたが、子ども理解から入ろうとする点はとても共感できました。自分が発達障害のグレーゾーンにいるためより興味をもったというのもあると思います。2018/11/28
mana
27
「発達障害」と決めつけるのは簡単だが、それ以上に、その子が適応できる環境づくりが必要だと。「困った行動」というのは、あくまで大人の目線。子供が発してるメッセージをじっと待つことが大切。また、誰のための診断、療育なのか?。グサリと刺さる部分が多い。社会が効率や協調性を重要視するために、発達障害が目立つようになり、レッテルを貼られるようになった。グレーゾーンの人が増えたのもそういうことだろうと思う。学校や社会の中で、区別なく人と関わり成長するというのは、障害の有無問わず大切なことだと感じる。2021/12/17
てるみ
5
それぞれの障がいについて分かりやすかった。覚えるまではまだまだだけどぱらっとめくって参考にしたい。理解や治癒は難しく、子どもが何を見てるのか教えて?という態度が大事だと思った。2014/08/13
akagiteaching
5
よい意味で医者らしくない本。「子どものことや障害のある子を持つ親の気持ちはわからない」というわからなさを自覚し,だからこそ子どもや親に学ぶという姿勢。このように言える小西先生の出自が気になるくらいよい本だった。おそらく原点が,障害のある親子の生活の中にある気がするのだけど,どうなんだろう?あと,「ほめて育てば自尊感情がつく」というありがちな言説に強烈な批判も。大事なのはほめるか叱るかではなく,子ども自身が,手ごたえを感じているのか,反省の芽があるかを見つめることだ,という意見に拍手喝さいしました。2013/05/26
-
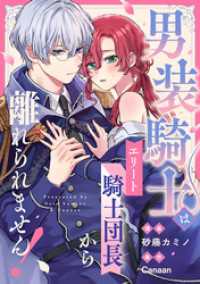
- 電子書籍
- 男装騎士はエリート騎士団長から離れられ…
-

- 電子書籍
- プリンセスの旅立ち【分冊】 6巻 ハー…
-

- 電子書籍
- 魔法科高校の劣等生(10) 来訪者編〈…
-
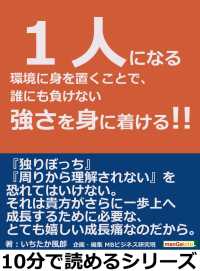
- 電子書籍
- 1人になる環境に身を置くことで、誰にも…
-

- 電子書籍
- ゼロからわかる アインシュタインの発見…




