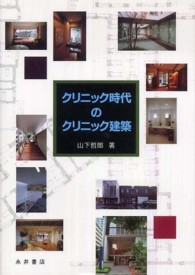内容説明
情報化、郊外化の著しい現代に必要とされる建築家像を探るべく、20人の建築家・社会学者らと対話した藤村龍至/TEAM ROUNDABOUTのインタビュー集。
対話者は、磯崎新、濱野智史、伊東豊雄、古谷誠章、小野田泰明、ヨコミゾマコト、難波和彦、山梨知彦、中山英之、田中浩也+松川昌平、鈴木謙介、五十嵐淳、小嶋一浩、梅林克+宮本佳明、迫慶一郎、岡部明子、井手健一郎、井口勝文。
[主な目次]
序 「アーキテクト2.0」とは何か 藤村龍至
第1章 1995年以後の都市・建築を考える
第2章 情報化を考える
第3章 郊外化を考える
目次
序 「アーキテクト2.0」とは何か
1 一九九五年以後の都市・建築を考える(一九九五年という切断と、それ以後の建築家像)
2 情報化を考える(ネットと建築をあえて混ぜて考える インタラクティブなプロセスを実現する意思 今、「メディアの錯綜する森」というコンセプトを振り返る ほか)
3 郊外化を考える(濃密な場所を設計するための想像力 なぜ建築家が都市について議論する必要があるのか!? 共同体の経験と設計の方法論の関係 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
伊藤康人
1
藤村龍至さんが、建築家、都市計画家、社会学者の一線級の人物たちと、「情報化」「郊外化」をキーワードに、2011年以降の建築家の可能性を討議していく内容。藤村さんの質問が非常に的確で、対談集ながら濃密な論文を読んでいる感じ。個人的には五十嵐淳さんの、建築家が都市をメインテーマに捉える意味がわからないというのには強い共感を覚えた。都市の分析などスケールの大きい話はディベロッパーや社会学者が担い、建築家は愚直に人にとって良いなと思える空間をデザイ二ングしていくことが本質なのではと思う。とにもかくにも建築家の職能2014/09/05
mym
1
建築家というと理論家というより技術者、または芸術家という印象を持っていたが、理論的なものを具現化するのが建築家ではないか。抽象的なことを考えることはもちろん重要だが、それを現実に機能させないと意味はない。そうした意味で、濱野氏、鈴木氏との対談から各章が始まり、建築家との対談へと移っていくという構成も興味深い。建物、まち、都市というような「モノ」を実際に作り人間に作用させる建築への興味が増した。2012/03/20
kukikeikou
0
工学主義/批判的工学主義/反工学主義…地域主義…批判的地域主義///アーキテクチャのアーキテクチャ/即アルゴリズム:援用アルゴリズム/宮台真司)郊外は地元になりえないー若林幹夫)郊外でも地元になりうる2014/01/08
izw
0
ソフトウェアやシステムの「アーキテクト」ではなく、元来の「建築家」。建築とシステムの類似点を発見でき、考えることの多い本だ。2012/04/18
きりんせんぱい
0
2012年に読んだ本
-

- 電子書籍
- 経営教育研究vol.15-no.1
-
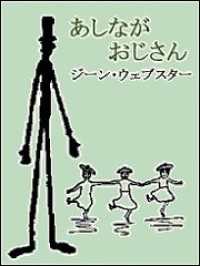
- 電子書籍
- あしながおじさん