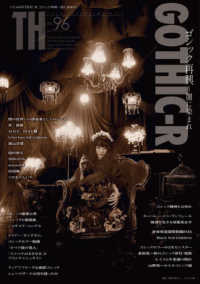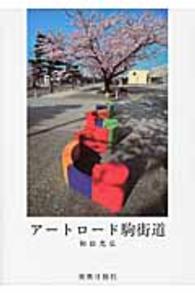内容説明
明治維新でなぜ皇族は急増したのか? 戦後、11家が皇籍離脱した「宮家」は、江戸時代には4家しかなかった。500年以上も遡らなければ天皇とつながらない人々は、なぜ「皇族」になったのか。明治天皇の意図、伊藤博文の狙いとは。徳川方についた北白川宮、首相になった東久邇宮、南京事件でGHQに尋問された朝香宮など、知られざる皇族たちの素顔を浮き彫りにし、皇族制度の誕生から消滅前夜まで、日本近代史の裏側に迫る!
目次
1 皇族の作られ方(枢密院会議 伊藤博文の迷走;宮家新立 曲げられ続けた原則;皇室典範増補;降下準則騒ぎ)
2 皇族と軍隊(明治初期の皇族と軍と戦争;軍学校と皇族たち;海兵での高松宮宣仁親王;皇族達の昇進と人事;戦場と皇族たち)
3 二人の皇族と事件(ドイツ女性との婚約;華族になった二人の少年;稔彦王帰国拒否事件;皇族総理大臣)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ツバメマン★こち亀読破中
24
王政復古以後の「皇族」というものの歴史的な変遷を豊富な資料を紐解き解説していて興味深い。皇位継承を安定させるための一定数の皇族を確保する必要があった一方で、尊厳を保ち、費用の問題もあり皇族を一定数に抑える必要があり、天皇、皇族、政治家、官僚がせめぎ合いを繰り広げる…。そんな歴史的な経緯も踏まえると、現代の皇位継承問題についても理解できます。2018/09/29
穀雨
6
第一部が皇族制度成立の経緯、第二部が皇族と軍部の関係、第三部がふたりの皇族の略伝と、テーマ的にややまとまりに欠けるきらいはあったが、豊富なエピソードで飽きることなく読み進めることができた。伏見宮系統の皇籍離脱がなければ今日の皇位継承問題もなかったのにとはたびたび考えてしまうが、当時はいわゆる直宮に青壮年の男性が6人もいらしたわけで、一概にそのときの判断を誤りと断じることはできないことがわかった。2021/06/23
うたまる
2
明治期に急増し敗戦時に急減した我が国の皇族についてのノンフィクション。日本史上における特異な事実を列記してくれているのは有難いが、箇条書き的な記述で散漫さと味気無さが玉に瑕だった。読了して思い知ったのは、宮家が多い方が皇位継承は安定するだろうが、顰蹙を買う者も現れ権威や敬意は下がるだろうこと。昭和、平成と続いてきた天皇の在り方が当たり前になってしまった現在、同じ水準を求められるのは誰であっても苦しかろう。それにしても「皇族方はとかく品行よろしからず…」「コンプリートリ・フール」とはひどい言われようだな。2024/09/20
takao
2
ふむ2022/11/28
塩豚葱串
1
江戸時代は4家しかなかったのに明治維新で数を増やした皇族という存在の知られざる一面に迫った本。 軍人になることが義務づけられていたので、敗戦後に巣鴨に入れられた皇族もいた。2019/06/08