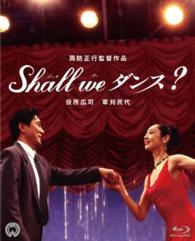内容説明
「古典コン」(クラシックコンサート)に行きましょう。CDにはない魅力、「古典」ゆえの楽しみ方、何を聴くか? 正しい拍手の仕方とは? 知りたかった疑問にお答えします。「のだめカンタービレ」クラシック音楽監修の〈もぎぎ先生〉が案内する、もっと楽しむための鑑賞の手引き。
目次
第1章 「古典コン」に行きましょう
第2章 古典コンの聴き方
第3章 拍手のルール
第4章 指揮者式手記
第5章 名曲の個人情報
第6章 数合わせ 交響曲のカレンダー
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
morinokazedayori
34
★★★★著者はN響オーボエ奏者で「のだめカンタービレ」の音楽監修でも知られている。終盤の楽典や楽曲解説の部分は読むのが若干しんどかったが、全体的にユーモラスな語り口で、著者の他の著作同様面白く読めた。拍手の作法は国によって違い国民性が表れるが、演奏者からみて、どういう拍手だとどう感じるかが事細かに語られていて興味深い。一番よかったのは、指揮者としての経験を語っている章。指揮の勉強法やオケとの関わりについて詳しく書かれていて、スコア片手にCDを聴きたくなった。2016/02/17
のぶ
32
演奏会で聴衆のマナーの悪さにうんざりしていた時に、偶然見つけた本。全編が拍手について書かれているわけではないけど、拍手の事は章の一つにあり、内容は自分の思っていたこととほぼ一致していた。ただ非常に共感した一言「沈黙が最大の喝采になる事もある」と。よく引合いに出される曲だが、マーラーの9番や悲愴なんかは、終局後どれだけ沈黙が続くかでその日の感動が違うと自分も思ってます。音楽を聴きに行って何で沈黙が、と思われるかもしれませんが、これ本当なんです。2015/08/21
G-dark
15
クラシック音楽に関する基礎知識や、「演奏会に行くならどの客席が良いの?」「どんな服装で行ったら良いの?」といった素朴な疑問、「どのタイミングで拍手をすれば良いのか分からない」「他のお客さんは音楽をとてもよく理解しているようなのに自分は素人だ」といった不安にまでアドバイスをくれる本。クラシックコンサートは敷居が高いものですが、この本を読んだ後は以前よりも気軽に行けるようになると思います。隣の席の人の迷惑行為(イビキなど)についても書かれていて、わたしは読んでいて「あるある!」と頷きっぱなしでした。2020/09/15
Nobuko Hashimoto
10
茂木さんといい宮本文昭さんといい、陽気でエネルギッシュな人が地味で難しいオーボエを演奏していると反動で指揮もしたくなるのだろうか。茂木さん指揮ののだめ音楽会は、実に盛りだくさんなプログラムでした。この本も、初心者も楽しめるようにとオヤジなギャグ満載。そのわりに音楽用語が説明なくぽんぽん出てきたりなんかして、かえって訳がわからなくなっているところもありますが、そんなノリが嫌いでなければクラシック音楽に親しみがわくかもしれません。でも、むしろクラシックに多少なじみがある人の方がニヤニヤ楽しめるかもしれません。2015/01/29
moani
3
ギャグ?面白かったですよ 自分がモーツァルトやハイドンにあまり興味がわかない理由が良くわからなかったけれど、その解釈が書かれていてなるほどと思った。いつかその素晴らしさがわかるようになったらいいなあ。そういえばバレエに興味を持ったきっかけが、バレエそのものではなくカーテンコールの拍手だったことを思い出した。こんな凄い拍手は一体どんな演技に対して注がれているものなの?と。色々読み取れて面白い拍手。著者の本を他にも拝読したい。2014/07/22
-
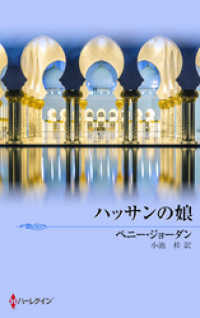
- 電子書籍
- ハッサンの娘 ハーレクイン
-

- 電子書籍
- 魔人探偵脳噛ネウロ モノクロ版 22 …