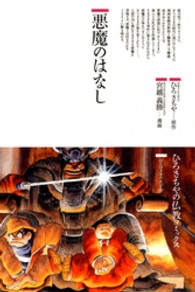内容説明
産業革命以来、「発展」のため進歩させてきた末の技術が、いま暴走している。その意味で、原発災害を原発だけの問題としてとらえてはいけない。これは「文明の災禍」なのである。私たちが暮らしたかったのは、システムをコントロールできない恐ろしい社会ではない。「新しい時代」は、二百年余り続いた歴史の敗北を認めるところから始めることができるのである。時代の転換点を哲学者が大きな視点でとらえた、渾身の論考。
目次
序章 供養―死者と向き合う
第1章 衝撃―自然の災禍、文明の災禍
第2章 群衆―イメージの支配
第3章 時間―営みをつなぐ
第4章 風土―存在の自己諒解
第5章 共有―何かがはじまっていた
終章 自由―イメージとは異なる世界
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うりぼう
50
私の今年のベスト1になる。3.11後の私の焦燥感をある程度満たしてくれた。内山先生の思想が全力で問う。日本の伝統社会は、自然とともに、死者とともに生きた社会。原発の災禍に魂の救済はなく、身体の折り合いがつかない。今回、被災地以外の人も知性と身体と生命に衝撃を受け、後の2者は、頭では整理できない。現代文明は、イメージに支配され、そのイメージへ信頼が崩壊した。今一度、自然と死者との関係を問い、身体と生命をとおした関係づくりを意識し、文学的に語るグランド・デザインをローカルな範囲で描くき、具体化するときである。2011/10/17
Willie the Wildcat
23
日本の失ったもの。復興の意味。これらを考えさせられる。自然の恵みと禍い。感謝を忘れ何事も当たり前のように感じる。「虚像から実像へ、確かな生を取り戻す」に同感。そのための”コミュニティ”。しかもツールではなく確かな思想に基づくコミュニティ。日本人の原点を振り返ること、かな。一方で常にリスクを考慮した判断を求められるのも現実。適切な判断のための適切な情報量と内容、そこが難しい…。日本人、そして人間の英知を信じる。2012/02/05
calaf
12
「専門家=専門領域でしか考えられない人」なるほど、その通りかも...そして人はみな、何らかの意味で(分野で)専門家なんですよね...2011/11/21
yummyrin
8
2011年3月のフクシマから学ぶことは何か。情報を大量に受け取ると人間は適切な判断ができなくなる。誰かがわかりやすいように伝えている情報もフィルターがかかっている。今回のじこ事故は人間の未来への営みを破壊してしまった。 では、どうするのか。 それはローカルな生活。スローライフを送ること。当時テレビのchを3分の一にすれば無駄な電気を使わなくて済むのに、と強く思った。 でも著者のように恵まれた立場から考えるのは難しいな。2016/06/13
ceskepivo
6
東日本大震災は、地震・津波・原発事故で地域の生活・労働システムをすべて崩壊し、人々に大きな危機をもたらした。その修復は一般の人ではできないことが大きな特徴の一つ。災害では人々の思いやりが有効だが、原発災害はそうはいかない。これまで人々は過去の人々が作ってきた文化、文明、技術を未来につないで生きてきたが、原発事故はそれを不可能にした。復興のグラウンドデザインは、自然、死者との関係を受け継いでどんな町に復興させるか、文学的・思想的・文化的に語るべき。著者の主張がストンと胸に落ちた。2015/10/11